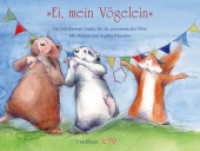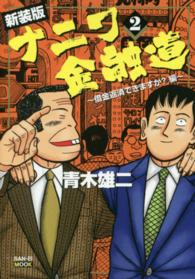目次
将軍足利義政・関東管領と足利成氏が争う 享徳3年(1454)~康正元年(1455)
千葉・佐竹・岩松などの一族が分裂し争乱へ 康正2年(1456)
五十子陣の構築と京より派遣された新公方 康正3年・長禄元年(1457)~長禄3年(1459)
所領支配の激変で“国衆”へと移行する武家 寛正元年(1460)~寛正4年(1463)
堀越公方の武蔵進軍と相次ぐ実力者の死去 寛正4年(1463)~応仁3年・文明元年(1469)
北関東の激戦と成氏の古河没落 文明2年(1470)~文明4年(1472)
駿河今川氏の内乱鎮定へ出陣する上杉軍 文明5年(1473)~文明8年(1476)
長尾景春の反乱で太田道潅が進軍を開始 文明9年(1477)
成氏が景春を見限り、道潅に討伐を指示 文明10年(1478)
連戦・連勝、景春を秩父へと追い詰める道潅 文明11年(1479)
将軍義政へ和議を乞う成氏 文明12年(1480)
都鄙和睦と道潅暗殺―戦乱、未だ止まず 文明13年(1481)~長享元年(1487)
著者等紹介
黒田基樹[クロダモトキ]
1965年生まれ。早稲田大学教育学部卒。駒沢大学大学院博士後期課程満期退学。博士(日本史学、駒沢大学)。現在、駿河台大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
20
1455年から1483年に至る、足利幕府の鎌倉→古河公方と関東管領の上杉氏との対立に始まる、関東、東海甲信越、南東北の広い範囲で発生した巨大な戦乱である。東日本世界の「世界大戦」とも言うべき大戦乱である。それを、整理し豊富な画像で理解しやすく書かれている。の、だが、前史を大胆に省いているので、何だか唐突に始まったとしか思えない。まぁ、「永享の乱」どころか、足利幕府成立からの関東のグダグダがあるわけである。そこを踏まえて言えば「万人恐怖」様と義政、後花園天皇はろくなことしとらんなあと思う他なし。2021/04/30
onasu
19
享徳3年(1454)年末、5代目の鎌倉公方足利成氏が関東管領山内上杉憲忠を謀殺したことに端を発した「享徳の乱」は足かけ29年も続いた。その間には、堀越公方が送り込まれたり、山内上杉家に叛旗を翻した長尾影春が道灌に連戦連敗しつつも再起を繰り返したりと、複雑怪奇な様相を呈した挙げ句、成氏が室町殿に仲介を願い(都鄙)和睦するが、4年後には両山内家の間で「長享の乱」が勃発。伊勢宗瑞の関東への進出を許して、両家は勢力を削がれるが、この期はどうにも分かり難い上に、道灌と影春以外取り上げられそうな人物もいないよう。2021/06/14
YONDA
13
同姓がたくさん出てきて誰が何してどうなったのか理解するのが難しかった享徳の乱。本書では丁寧に書かれているので、古河公方の成氏と関東管領の上杉氏との戦がこの乱の基本である。が、そこに同族の争いも加わって色々な上杉や千葉や結城やらも参加し、さらに長尾景春の乱もあって理解不能に陥るが、前述したようにこの本はとても丁寧に時系列を追って書いているので、完全とは言えないが今までよりも理解が格段に増します。この後の長享の乱も同書のように黒田先生に書いてもらいたい。2023/09/03
BIN
11
享徳の乱は応仁の乱の少し前1455年から29年続いた関東で起きた鎌倉公方足利VS上杉の争い。歴代鎌倉公方は何かしら上杉とやりあってだいたい負けてますが、この足利成氏は結構頑張って、序盤は結構勝ってるのが印象的でした。足利義政もまだ政治に関心があった時期なのか結構指令を出していた。終盤は太田道灌や長尾景春など有名所も参戦。図説と言う割にはもう少し図が欲しかったなあ。2022/09/19
フランソワーズ
9
鎌倉・古河公方成氏が父の仇上杉憲忠を謀殺したことに勃発した享徳の乱。その成氏と関東管領上杉氏を結集核として、山内・扇谷両上杉氏各々の家宰長尾氏・太田氏。成氏の奉公衆や関東・南奥羽の大名・国衆まで巻き込んだ戦乱が20年余り続く。その間、それぞれ諸将は自らの思惑によって離合集散を繰り返す。戦国時代の嚆矢といえるこの戦乱、諸将は分国の一円化に積極的に動き、また所務遵行の不全化に陥ったことにより幕府権力の低下を招いた。概説書としては手頃、それでも正直複雑すぎる関東戦国史(北条氏登場以前の)。2023/04/09
-
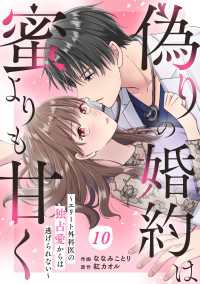
- 電子書籍
- comic Berry's 偽りの婚約…