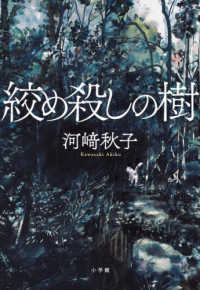内容説明
“忠臣”のイメージから解き放たれた武将31名の熱い生きざま!
目次
第1部 東国武将編(南部師行―陸奥将軍府で重用された八戸家当主;南部政長―糠部を支配する北奥の雄;北畠顕家―若くして散った悲劇の貴公子;伊達行朝―北畠顕家とともに転戦した奥州軍の中心;結城宗広・親朝・親光―信任厚い南奥の名門 ほか)
第2部 西国武将編(護良親王―尊氏打倒に燃える悲劇の親王将軍;楠木正成―後醍醐忠臣という虚像;楠木正行―“悲劇の武将”の実像;楠木正儀―“南朝将軍”の虚実;四条隆資―各地の南朝方と天皇を取り次ぐ公家武将 ほか)
余録 新田嫡流を支えた脇屋義助・義治
著者等紹介
亀田俊和[カメダトシタカ]
1973年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。現在、国立台湾大学日本語文学系助理教授
生駒孝臣[イコマタカオミ]
1975年生まれ。関西学院大学大学院文学研究科博士課程後期課程日本史学専攻修了。博士(歴史学)。現在、花園大学文学部専任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Willie the Wildcat
72
史料に基づき、31名の武将を紐解く。印象的な武将からはまず『北畠顕家』。奥州の猛者との対峙や二度に渡る畿内遠征以上に、後醍醐天皇に上奏で苦言を呈する姿勢が印象的。対照的な覇王『護良親王』。鎌倉宮でも垣間見ることができる存在感。前線に立ち続けたもう1人の南朝・征夷大将軍『宗良親王』は覇王とは対照的に、慰みと共に静けさを遺す。実務面では征西将軍『懷良親王』。武功はもちろんだが、中国・明との通交も光る。それにしても、三木一草の史料が少ない。その史料の観点では、護良親王の『紙背文書』が印象的。2022/02/20
鯖
24
逃げ若北条時行に顕家にモっくん千種忠顕に蛍丸の持ち主恵良惟澄あたりまでは知ってたけども、東国の武将は南部さんち含め全然わからんわ…。網羅っぷりがすごいけど、これ、別名G被害者の会だよね。顕家の上奏文について大内裏造営への批判するなら尊氏の天竜寺造営にも批判しないと不公平じゃんとか、僧侶や女官武士に官位もったっていうけど実力重視の大胆な人材起用じゃんとか、古今東西の一般的な政権批判じゃんと亀田先生が批判的な見方をされてるんですが、その批判をGにしたのがすごいんではと思う顕家の判官びいきな我であった。2021/08/20
サケ太
21
南北朝時代のおおまかな把握をしたら、ぜひこれを読んでほしい。漫画の影響だが、宇都宮公綱や諏訪直頼に興味をもった。個人的に南朝の最重要人物北畠親房についても面白く読めた。通して読むと、この時代の流れも理解できてくるわけだが、教科書でもなんでもざっくりと時代の流れは把握しておいた方がより魅力を感じ取れる。2021/09/25
六点
18
北は南部師行、南は恵良惟住まで…思わず「どちら様で?」と、言いたくなるような武将まで収録されている。無論、北畠顕家や懐良親王と言うビッグネームも最新の研究を手短に纏め収録されている。誰か国文学の研究者を連れてきて、児島高徳について論じてもらっても面白いと思った。まぁ、望蜀であるね。いずれにせよ、各編30P前後で、後醍醐天皇の「御謀叛」に付き合った武将たちの軌跡と研究の一端を見ることができ、実におすすめである。ぬこ田は北畠氏大好きなので参考文献の『伊勢北畠一族』を『日本の古本屋』で購入してしまった。2021/06/26
Francis
15
編者の一人亀田俊和先生のファンなので買いました。と言っても先生の書かれたのは北畠顕家だけなのだが。とは言えみなさん本当に良く調べてお書きになってます。これまでの「太平記」に依存した見方でなくあくまで一次史料に立脚して人物像を描く姿勢は土の著者も一貫しているのが良い。征西将軍宮懐良親王が意外や意外厭世的な面があったのは驚き。はるか信濃国にいた宗良親王に和歌を届けたのもお互いの境遇が似ているのを知っていたからなのだろうなあ。2021/08/25