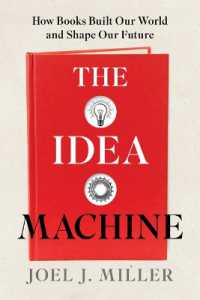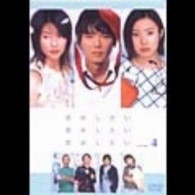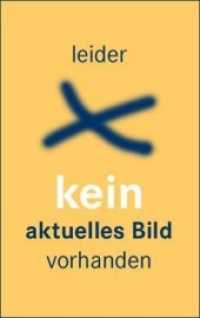内容説明
戦場であげた武功は、将軍や守護からどのように評価されたのか?軍勢催促状・着到状・軍忠状・挙状・感状・充行状などから浮かび上がる武功の現実!
目次
第1部 参陣から恩賞給付までの流れ(参陣から軍功認定まで;恩賞を受けるまでの複雑なプロセス)
第2部 軍勢催促・軍功認定・恩賞給付の再検討(軍勢催促をめぐる諸問題;軍奉行・侍所による実検手続き;軍忠状の型式と提出先の問題;恩賞申請と給付の問題)
第3部 南北朝期の戦闘の実像に迫る(合戦の結果をも左右した兵粮;南北朝期の戦闘の実態)
著者等紹介
松本一夫[マツモトカズオ]
1959年、栃木県宇都宮市生まれ。1982年、慶應義塾大学文学部卒業。2001年、博士(史学)。現在、栃木県立上三川高等学校長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のれん
14
日本の文書主義は七百年前でも働いているということが分かる一冊。出陣から功績申請、感謝状(報酬)全てに文書が必須で、どのように戦い首級をどのようにして勝ち取ったかまで書かれる始末で、そこまでした上で疑義がなされるのだという。 今の役所と良い勝負の面倒くささ。それでいて功績の審査が厳しい所まで一緒。競争原理を働かせようというより資産の出し渋りが見て取れる。 何時の世も現場出世は厳しいものだと伝わる。 著者は学校の教頭の立場でもあるらしく、冗談一つ無く読みやすい文章が勤勉教師を思わせ印象的。2020/08/01
Toska
13
『鎌倉時代の合戦システム』(https://bookmeter.com/books/19488643 )より前に出た著作だが、扱っている時代はこちらの方が後(南北朝期)。実際、この頃から軍事行動の大規模化に伴い恩賞給付の複雑化とシステム化が進展し、文書史料も前代より格段に増加するとのこと。そんな中、足利尊氏の書状は感激屋ですぐ恩賞をやってしまう本人の性格をよく表している。日本史上、最も味のある手紙を書く人物の一人ではあるまいか。2024/11/17
六点
12
よくネットで「ムロマチ・メソッド」という単語を目にするが、その室町時代になる直前、武士の「仕事」である「戦争」での手柄を如何に恩賞に変換するのか?と、意外と認知されていないその手続を中心に、武士の人事評価を中心にした第一部と、当時の軍事行動が如何様に行われていたのか?その有り様を、余り公知されていない側面から迫った第2部から構成される。当時の事務官僚の仕事の煩雑さを見ると、本当に人の世は常にキツいという感想しか出てこない。また、足利尊氏の気前の良さはやはり抜きん出いていた事を思い知らされた。2020/12/27
feodor
9
鎌倉時代の元寇などと比較しつつ、恩賞給付にまつわる文書の流れを追っていくのが前半。出動要請があったりなかったりして、出陣したら着到状という文書を出して、また功績を上げたら軍忠状を出してチェックを受けて……と結構文書行政がしっかりしているのだなあと思う。ただ一方で、尊氏直筆の書状とかでぽんと恩賞ゲットというのもあったり、逆に上官から一括申請するから戦場を申請のために離れないでと通達していたりと戦況によるものも多いよう。書状ばかりだけれども、案外興味深い。後半は戦い方の部分に触れ、こちらもおもしろかった。2020/08/01
akiakki
8
戦乱の時代でも戦争勃発から恩賞給付まで意外としっかりとした行政手続きがあった。完全には制度化されていないので事後処理や、現場の動き優先な事例もあるが、それでもインプット・アウトプット・評価がちゃんとシステム化されていたとは。逆に未だに紙ベースで処理を進めてるところは南北朝時代から進歩してないってことでは。恩賞と言えば土地ですが、ゲームのように一瞬で色が変わるわけもなく、行政手続きが進まなくて土地が貰えない、書類上は自分の土地になっても残党が立てこもり引き渡されない、と現実的な事例もあったようです。 2022/09/28