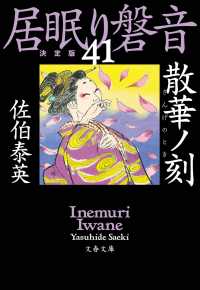内容説明
全国各地の城下町・港・街道などは、どのようなプランで開発・整備されたのか。文献史学と考古学を合わせた学際的な観点から戦国大名領国の特質に迫る。群雄割拠の戦国時代、大名や領主が目指した都市構想とは?
目次
中世日本の「土木」と「インフラ」―はしがきにかえて
第1部 戦国大名・国人領主の土木政策と城郭(十六世紀後半における安芸国吉川氏の土木事業;豊後府内における道路と土木工事;『上井覚兼日記』にみる土木事業―城郭普請を中心に ほか)
第2部 中世の都市設計(大内氏の町づくり―中世都市山口の“原点”の発見;戦国大名相良氏の「八代」整備;中世博多の都市空間と寺院「関内」)
第3部 中・近世の社会基盤整備(平安~室町期における生活の中の水を考える―古典文学作品と絵画資料を中心に;朝鮮出兵期の長宗我部領国における造船と法制;中・近世における貿易港の整備―博多・平戸・長崎の汀線と蔵 ほか)
著者等紹介
鹿毛敏夫[カゲトシオ]
1963年生まれ。広島大学文学部史学科卒業、九州大学大学院人文科学府博士後期課程修了。名古屋学院大学国際文化学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
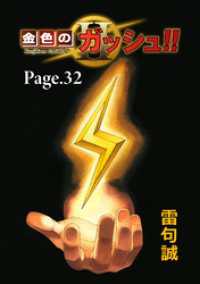
- 電子書籍
- 金色のガッシュ!! 2【単話版】 Pa…
-

- 電子書籍
- 人気絶頂女優の私が、急死してぽっちゃり…
-

- 電子書籍
- 魔女と魔性と魔宝の楽園~追放された転生…
-
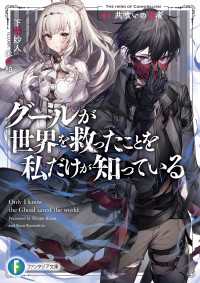
- 電子書籍
- グールが世界を救ったことを私だけが知っ…