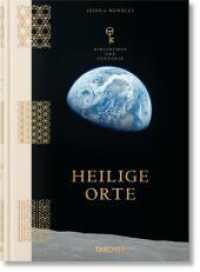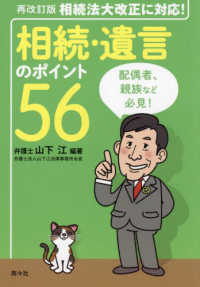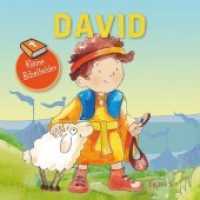内容説明
高野山や興福寺、一向一揆や寺内町など多種多様な宗教勢力を抱え、独自の地域圏を形成した南近畿は、どのように武家権力と結びつき、政治史を彩ったのか。河内・摂津・和泉・大和・紀伊を新たに「南近畿」として把握し、権力や城郭から地域性を読み解く。
目次
第1部 南近畿の在地社会と城郭(紀伊国における守護拠点の形成と展開;山城から平城へ―一五七〇年代前後の畿内と城郭;文明の和泉国一揆と国人・惣国;戦国時代の大和国にあった共和国;織豊期の南近畿の寺社と在地勢力―高野山攻めの周辺)
第2部 戦国時代の河内と権力(河内王国の問題点;木沢長政の政治的立場と軍事編成;三好氏の本拠地としての河内)
著者等紹介
小谷利明[コタニトシアキ]
1958年生まれ。八尾市立歴史民俗資料館長
弓倉弘年[ユミクラヒロトシ]
1958年生まれ。和歌山県立桐蔭高等学校教諭(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
BIN
7
南近畿は今の都道府県でいうと大阪、奈良、和歌山を指してます。その南近畿の戦国時代の論文集になります。個人的には雑賀衆あたりを期待してましたが、どちらかというと信長登場前の応仁の乱直後とかの記載が多く、ほとんど読んだことがない内容だったので期待通りではないものの楽しめました。河内王国という表現があるんですね。2019/08/03
四不人
3
「南近畿」という括りが新しいのだろう。通読すると、南近畿が畠山氏と根来寺の世界なんだなあ、と思う。むろん熊野や高野山もあるが、主役となるプレーヤーは畠山と根来。地域史を動かす動力は畠山の内紛と根来の和泉進出。南近畿の変動は南から来るんだな。ちょっと面白かった。2019/09/08
こずえ
1
紀伊など京から少し離れたところの戦国時代の動静がまとまっていておもしろかった