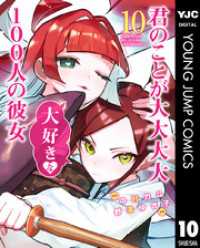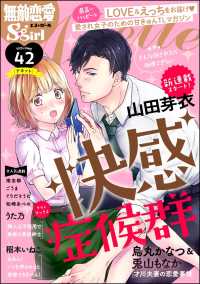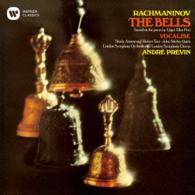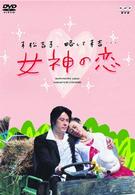内容説明
徐々にすれちがう二人の思惑。義昭はほんとうに信長の操り人形だったのか。「天下」を巡る二人の関係をていねいに分析し、最新の研究成果から義昭政権の権力構造に迫る!
目次
第1章 足利将軍と畿内の政情
第2章 覚慶の諸国流浪と「当家再興」
第3章 足利義昭の上洛と室町幕府の再興
第4章 幕府の再興と義昭の政権構想
第5章 義昭政権の軍事力
第6章 織田信長と幕府軍の軍事指揮権
第7章 「元亀の争乱」における義昭と信長
第8章 足利義昭の蜂起と幕府の滅亡
第9章 幕府滅亡後の信長による「幕府再興」と政権構想
終章 義昭の「天下」と信長の「天下」
著者等紹介
久野雅司[クノマサシ]
東洋大学大学院文学研究科日本史学専攻博士後期課程退学。現在は、東洋大学・いわき明星大学で非常勤講師を務める。専門は、日本中・近世移行期(戦国・織豊期)。研究テーマは「織田政権の権力構造論」(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HaruNuevo
10
現実を見ずにすぐに ムキーっとなって、あちこちにキャンキャンと自分勝手な手紙を書いては自ら秩序を乱そうとする傀儡将軍と、彼をてのひらで転がしながらもブチキレる信長。 なんか歴史小説ばかり読んでいると、どうしてもそんなイメージになってしまうわけだが、実際に史料を丹念に関連付けながら読み込んでいくと、実相は全く異なる。 足利将軍家の権威を尊重し、『天下』における秩序を重要視し、足利義昭との協調を図った信長。 実質的に権威と軍事力をまだ有していた足利義昭。 歴史小説ばかりではなくこういった本も摂取せなアカンな2023/07/14
MUNEKAZ
10
足利義昭政権について。結果論で信長の「傀儡」とされることが多いだけに、その奉公衆や任命した畿内の守護たちが、対三好戦などで実際に活躍していたり、幕臣の信長に対する反目に義昭自身が引きずられているのは興味深い。また信長も保守的・復古的な態度で、「天下」の政治については義昭を尊重し、極力介入しない姿勢を維持しようとしているのも面白い。同じ天下の静謐を望みながらも破綻した義昭と信長の関係を思うと、軍事政権でありながら軍事力を他者に頼らなければならない室町幕府の限界が感じられる。2017/12/06
chang_ume
9
足利義昭傀儡説について史料を細かく見ながら従来説に再検討を加える。永禄13年『五ヶ条条書』を義昭から信長に委任された「天下静謐維持権」とした箇所が本書のポイントで、義昭・信長協調体制を元亀3年末まで下降させるなど新解釈が多い。また畿内守護と奉公衆からなる「幕府軍」に実態を見出した点も大きい。近年の信長研究を素直に敷衍すると(著者は神田千里氏のお弟子)、義昭主体の公儀形成は本書のように再評価され得ると思った。加えて元亀2年普請の勝龍寺城など、織豊系城郭の成立過程にも影響するだろう。2023/04/16
Toska
5
「信長英雄論」「三好天下人論」との二正面作戦を強いられつつある義昭幕府の再評価。統治システムは意外にしっかりしており、軍事的な動員力も侮れない(従来は全て「信長の戦争」イメージに包摂されてしまっていた)。ただ、義昭本人の失政と土壇場での判断ミスが全てを台無しにしたという印象。単なる「実は有能」論では終わっていない。成功も失敗もひっくるめて、義輝よりはるかにスケールのでかい人物だったのでは?あとは、義昭の判断に影響を与えた幕臣(上野秀政など)についてももう少し突っ込んでもらいたかったところ。2022/01/28
兵衛介
4
従来の織田信長・足利義昭像の大転換を迫られる本。研究者の間では近年常識化しつつあるこれらの研究成果がここに一般書として刊行され、広く読まれる機会が提供された。歴史に興味のある層には強烈な知的刺激となるだろう。しかし、ここで明らかとなった保守的な織田信長像は、少なくともルイス・フロイスら宣教師らの遺した史料を通して見た織田信長像とは大分異なる。これは宗教的偏見を持つ外国人の偏った見方として片付けて良いものか。個人の性格と政治家としての姿勢は別であり何ら矛盾はないものと考えるべきなのか。2021/07/11