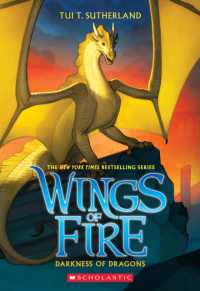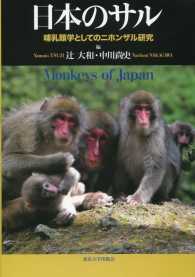内容説明
現代アメリカ文学を代表する作家のひとり、アレクサンダル・ヘモンの最初期短篇集。
著者等紹介
ヘモン,アレクサンダル[ヘモン,アレクサンダル] [Hemon,Aleksandar]
1964年、旧ユーゴスラヴィアの構成国だったボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国の首都サラエヴォで生まれる。大学卒業後、メディア関係の仕事を経て、1992年に文化交流プログラムによって渡米。滞在中にサラエヴォがセルビア人勢力によって包囲されたことで帰国不能になり、そのままアメリカに留まる。母語ではない英語で作品を発表するようになり2002年に発表した長編『ノーホエア・マン』で高く評価される。現在はプリンストン大学でクリエイティブ・ライティングを教えるほか、『私の人生の本』のようなエッセイ、音楽、映画・ドラマ脚本といった分野でも活動している。映画『マトリックス レザレクションズ』ではラナ・ウォシャウスキー、デイヴィッド・ミッチェルと脚本の共同執筆も務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヘラジカ
42
濃厚濃密。ほんの数行読んだだけで呑まれるような、圧されるような空気に当てられる。ありきたりな表現で恐縮だが、まるで短篇小説とは思えない量感の傑作ばかりであった。どの作品もインパクト大で忘れがたいが、強いてお気に入りを挙げるなら、作中でも屈指のページ数を持つ「ブラインド・ヨゼフ・プロネク&死せる魂たち」、柴田元幸氏イチオシでトップを飾る「島」とそれに続く「アルフォンス・カウダースの生涯と作品」の三作。いずれも今年の短篇小説ランキングを作るならば間違いなく入る逸品だ。2023/11/12
夏
32
著者は旧ユーゴスラヴィアの構成国だったボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエヴォで生まれた。彼は1992年に渡米し、アメリカ滞在中にセルビア人勢力によりサラエヴォが包囲されたことによって帰国不能になり、そのままアメリカに留まることになった。これはそんな著者が母語ではない言語で書いた8編の短編集である。「故郷消失者は言語の中でのみ生きることができる。たとえどこにいようが故郷には決していないのだから」という帯の言葉が胸に刺さった。著者だけでなく、このような思いをしている人が世界中にいるのだと思った。星4.5。2025/12/24
まこ
10
作中の表現の多くが汚さや恐ろしさ、さらには死と直結して作者の子ども時代の壮絶さを伺わせる。作者個人の歴史とボスニアの歴史を照らし合わせて、当時抱いていた憧れを振り返る。アメリカに移住しても、アメリカの自由さを感じることはないのに、永住権を持ってることをアピールする矛盾。作者の本当の居場所はどこか2024/03/03
ぱせり
9
紛争下で日々命を脅かされる生活と、そういう危機からは遠くにいながら(いるために)狂気に近い苦しみに独り耐えること。迫害、虐待を受けながら、死ぬこともできずに生かされていること……。形を変えて語られる残酷な場面は、きっとどれも事実なのだ。それなのに、どの場面も静かでお伽話めいている。郷愁さえも感じるほど。2024/06/26
masabi
7
「ゾルゲ諜報団」ゾルゲに関連する註釈が本編の物語以上に気になった。ナボコフの作品でも註釈に仕掛けを仕込んだ作品があったなと連想したが、異国の地で英語で執筆した共通点もあるようだ。「心地よい言葉のやりとり」歴史にヘモン家の人間を関わらせようとするのだが、家系の神話創造といった趣き。その記録のためにビデオカメラを回していても編集の手が加わった仄めかしがあり、なんとも胡乱だ。故郷での少年時代、故郷喪失、戦争の最中の書簡形式と作者のバックグラウンドが色濃い。2025/02/19
-

- 電子書籍
- 拾ったのは狐の娘でした【タテヨミ】第6…