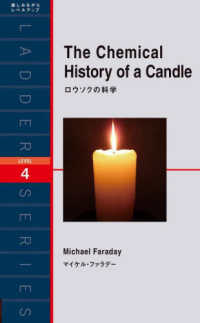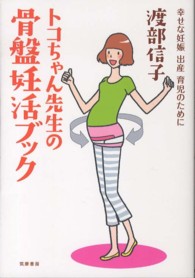目次
二重のまち
交代地のうた
歩行録
著者等紹介
瀬尾夏美[セオナツミ]
1988年、東京都足立区生まれ。土地の人びとの言葉と風景の記録を考えながら、絵や文章をつくっている。2011年、東日本大震災のボランティア活動を契機に、映像作家の小森はるかとの共同制作を開始。2012年から3年間、岩手県陸前高田市で暮らしながら、対話の場づくりや作品制作を行なう。2015年宮城県仙台市で、土地との協働を通した記録活動をする一般社団法人NOOK(のおく)を立ち上げる。現在も陸前高田での作品制作を軸にしながら、“語れなさ”をテーマに各地を旅し、物語を書いている。ダンサーや映像作家との共同制作や、記録や福祉に関わる公共施設やNPOなどとの協働による展覧会やワークショップの企画も行っている。単著に『あわいゆくころ 陸前高田、震災後を生きる』(晶文社)が第7回鉄犬ヘテロトピア文学賞を受賞。文学ムック「ことばと」vol.2で初小説「押入れは洞窟」を発表した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
42
二重のまち、この意味が、読み進めるに従い、こころに迫ってくる。想像するに難い。消し去ってしまうわけにはいかないという思いと、生きていくという思いと、それが重なること響きあう。時間の流れの中で、時間が過ぎるのに身を委ねることも、時には必要なのだろうかと思う。どう、自分の中に収めるのか・・・難しい。2022/09/21
tenori
31
東日本大震災後に陸前高田市を中心にボランティアとして活動し、現在も伝承・継承活動を続ける瀬尾夏美さんの記録で三部構成。【第一部】嵩上げ後の街を「上の街」震災時点の街を「下の街」ととらえ10年後の2031年にその場所で暮らす人達の想いを想像した、瀬尾さんらしいスケッチと短文で四季を綴った絵本のような作品。【第二部】瀬尾さんが主宰したワークショップの参加者が見聞した被災関係者の「声」を瀬尾さんの言葉でまとめたもの。【第三部】瀬尾さんの活動記録を日記として記したもの。丁寧に想像することの大切さが伝わる。2021/03/26
ツキノ
26
東日本大震災のボランティア活動を契機に2012年から3年間、岩手県陸前高田市で暮らしながら対話の場づくりや作品制作を行なっているという著者。宮城県を中心として民話の採訪を行う「みやぎ民話の会」の活動にも同席したとのこと。「二重のまち」は、かつてのまちの営みを思いながらあたらしいまちで暮らす2031年の人々の姿を想像して描いた物語。映像作家の小森はるかと共同で映画化されている(観たい!)。後半の「歩行録」は2018年3月から2021年2月までの記録。所々に聞いたことばが挟み込まれている。2021/05/18
ぱせり
7
このまちで生まれ育ち生活していた人たちの思い(生きているひと、亡くなったひと)の結晶のようだ。「復興」という言葉が、物語をしっかり抱き込んでいてくれたら。わかったようなことは何も言えないけれど、せめて聞かせてもらいたい。下のまちが抱いているたくさんの物語を。生まれ始めている上のまちの物語を。二重のまちの物語を。2021/04/07
ガラスのバラ
6
震災ボランティアの後、陸前高田に移り住み、まちの人達の話を紡いでいる作者。復興工事で嵩上げされた土地を上のまちと呼ぶ。見た目は新しく復興が進んでいるかも知れないが、かつての町跡は感じられない。この土の下に下のまちがあって、かつてそこで生きていた人達の思い出やらすべてを埋めてしまってよかったのか。移り住んできた人達や新しく生まれてきた子供達は目に見えない下のまちのことを知らない。上のまちとはつながっているんだよ。静かだけど重い言葉の響きに満ちた作品で、色んな思いがあることを知り、寄り添いたいと思えた。2021/06/27