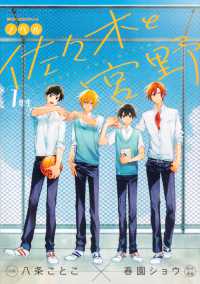内容説明
結婚・出産の「ご報告」、パタハラ、洗濯男子、テレワーク、親バカ文化…。公私領域の再編に注目し、家族ブームの背景を読み解く。
目次
1 「私ごと」が国民的関心事に?(「公私混同」の意味が変わった;進次郎&クリステル婚が象徴する「私ごと」の劇場化;ソーシャルメディアの普及と「ご報告」ブーム;家族を語る行為を支えるもの;「家族が大切」という意識の高まり)
2 家族の語られ方が2010年代に変わった(家事とCMと男と女;ぼく作る人&洗う人―料理男子、洗濯男子の登場;パパブログにみる「親バカ」文化の隆盛;誰が「父」として語っているか;「ママだけど…」という役割規範への抵抗)
3 エンタメコンテンツとしての家族ストーリー(家族を問い直すメディア作品への社会的な注目;ハリウッド映画の新旧のヒーロー;「父」を語る欧米文化の輸入;「ご報告」に反映された、父としてのあり方)
4 家族をめぐる政治・経済的な思惑とメディアの関与(家族に関する政策とメディアの連動;国家的リスクと「家族の絆」言説の強化;「イクメン」ブームを支えたもの;レジャーの流行と家族の休日の関係)
5 “公”“私”の揺らぎと家族の変容(浸食し合う“公”“私”の境界線;家事や育児は押し付け合うものなのか;「家族の絆」言説の過熱化とその弊害;家族のストーリーが求められる理由)
著者等紹介
橋本嘉代[ハシモトカヨ]
筑紫女学園大学現代社会学部准教授。1969年、長崎県佐世保市生まれ。上智大学文学部新聞学科を卒業後、集英社に入社。女性誌編集に携わる。退職後、ウェブマガジンのプロデューサーやフリー編集者などを経て、2014年から大学教員に。立教大学大学院で修士号(社会学)、お茶の水女子大学大学院で博士号(社会科学)を取得。専門はメディアとジェンダー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
カッパ
ありんこ
たいこ
にこまる
トム