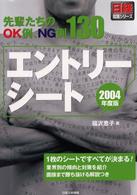- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
内容説明
子どもが望む授業をしていますか?自分の能力を使って活動できる授業。それを実現するために、授業改善の方法、授業実践の数々を紹介。絵本を題材にした授業展開、医療的ケアについてなど。
目次
1章 授業改善に向けて(子どもが活動する「子ども主体」の授業づくりとは1;子どもが活動する「子ども主体」の授業づくりとは2 障害の重い子どもの自己決定の力を支え育むために ほか)
2章 子どもが活動する「子ども主体」の授業と授業改善(目と手と全身で感じるあそび―心の動きを伴って;自分から動いていく子どもたちの姿をめざした授業づくり ほか)
3章 絵本を題材とした授業の展開(絵本を題材とした授業の展開を考える―「はらぺこあおむし」を通して;「はらぺこあおむし」その2 ほか)
4章 医療的ケアの必要な子どもの授業の取り組み(医療的ケアが必要な子どもの授業づくりを考える;不定期な吸引を必要とする子どもの授業づくりを、一日の日課から考える ほか)
資料
著者等紹介
飯野順子[イイノジュンコ]
昭和41年3月、東京教育大学教育学部特殊教育学科卒業。肢体不自由教育を専攻。昭和41年4月より、江戸川養護学校・11年(肢体)、府中養護学校・7年(肢体)を経て、昭和59年から10年間、東京都教育委員会にて、指導主事として就学相談を担当。その時、医療的ケアの課題に出会い、「救急体制整備事業」等の課題に行政と共に取り組む。平成6年から、都立多摩養護学校(知・肢併置)、港養護学校(知的)、村山養護学校(肢体)の校長を8年間勤める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- DEKIRU英会話magazine17…
-

- 電子書籍
- コミュニケーション100の法則