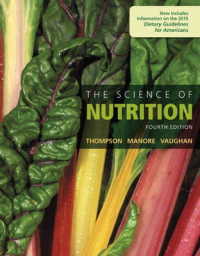内容説明
明治29年、清水寺の袂に創設された京都市立陶磁器試験場では京焼の近代化を目的に、陶磁器の窯や素材の研究からデザインに至るまで、多様な研究が行われていた。後に増設された附属伝習所では、若き日の河井寛次郎、濱田庄司、小森忍らが教鞭をとったことで知られる。五代清水六兵衛、楠部彌弌、近藤悠三などを輩出したこの附属伝習所は、近代日本の陶芸教育の中心と呼べる場所だった。
目次
大正時代における京都市立陶磁器試験場及び附属伝習所の活動について(朝日焼松林家蔵;松林鶴之助関係資料;陶磁器試験場設立までの京都の窯業;京都市立陶磁器試験場の研究成果;二代場長植田豊橘;大正五年(一九一六)陶画科
大正六年(一九一七)特別科)
日記(大正五年)
日記(大正六年)
著者等紹介
前崎信也[マエザキシンヤ]
立命館大学衣笠総合研究機構専門研究員、京都市立芸術大学芸術資源研究センター非常勤研究員。1976年滋賀県生まれ。龍谷大学文学部史学科卒業、ロンドン大学SOAS修士課程(中国美術史)修了、米国クラーク日本芸術研究所勤務、中国留学などを経て、2008年ロンドン大学SOAS博士課程(日本美術史)修了、2009年に同大学よりPh.D.(美術史)取得。同年より立命館大学で勤務し、2014年4月より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。