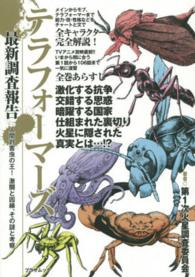出版社内容情報
年中行事とは、季節の巡りに従って展開された暮らしの図式です。暦や方位の項目や昔話・伝説にも触れ、イラストを多用して解説。年中行事のいわれを知っていますか?
日本列島には四季があります。その上.南北に細長く自然や文化が実に多彩で豊かです。その豊かさが立体感をもって現れるのが.年中行事と祭礼です。
春には花が咲き実を結ぶことを祈る祭。神様を歓迎して豊作を祈ります。
夏には水の祭。海や川から先祖霊を迎え、厄神を退散してもらいます。
秋には収穫感謝祭。「花鳥風月」とりわけ月の霊の訪れを待ちます。
冬には神様をもてなす祭。季節が順調に巡りくることを約束してもらいます。
本書では、これらの伝統行事と祭礼を中心に、現代の行事、記念日、外国の行事も取り上げ、イラストを多様して解説しました。理解の助けとなるよう、暦や方位の項目も設け、多くの昔話・伝説にも触れています。
本書の冠婚葬祭の項目で、年中行事とは、季節の巡りに従って展開された暮らしの図式である、としました。読者の方々には、できれば、正月から順番に読み進めていただくよう願っています。必ずや、なるほど、との実感が得られると思います。
第1章
1 正月 迎える心と形●1月1?7日
2 初夢・書き初め 1年の計は「2日」にあり●1月2日
3 初詣・年賀状の歴史 年始回りから国民的行事●1月1?7日
4 歌留多 声に出して読めばわかる百人一首
5 七草 若菜を食べて清明の気を受ける●1月7日
6 鏡開き 餅は神様のお下がり品●1月11日
7 旧暦と新暦 行事の理解のために?
8 小正月 庶民の暮らしから生まれた正月●1月13日?15日
9 二十四節気と雑節 行事の理解のために?
10 節分 鬼追いは福呼び●2月3日ころ、立春の前日
11 初午 お稲荷さんは現世御利益の最高神●2月最初の午の日
12 建国記念の日 日本と日本文化を考える機会に●2月11日
13 艮と乾 行事の理解のために?
14 バレンタイン?デー 愛の伝え方●2月14日
15 雛祭り 桃の節句●3月3日
16 東大寺お水取り 春を呼ぶ聖水●3月13日
17 涅槃会 仏の別れ●3月15日
18 お彼岸 春秋2回の先祖供養●3月18?23日ころ/9月20日?27日ころ
19 花見 春の訪れを皆で楽しむ●3月下旬?4月上旬
20 イースター キリストの復活と春の再生を祝う●春分後の満月後、 最初の日曜日
第2章
21 エイプリルフール 道化が演じる「逆さま世界」の寓喩●4月1日
22 鎮花祭 「やすらい花や」散る花を惜しむ●4月上旬
23 卯月八日と灌仏会 めでたきことに寺詣●4月8日
24 日吉山王祭 「7年見ざればことごとく見尽くし難し」●4月12?15日
25 母の日・父の日 敬いと絆と●5月第2日曜日/6月第3日曜日
26 八十八夜 国産初の暦の誕生●5月2日ころ
27 端午の節句 菖蒲の節句●5月5日
28 田植えと女性と菖蒲 「苗の植え初め、稲つる姫に参らしょう」
29 當麻寺練供養 極楽往生の野外宗教劇●5月14日
30 葵祭 「葵かづらの冠して」●5月15日
31 神田祭 江戸っ子の誇り「天下祭」●5月12?15日
32 三社祭 海から上がった観音様●5月18日に近い金?日曜の3日間
33 曽我の傘焼 東国一の御霊神を祀る日●5月28日
34 更衣 心と体のために暮らしに目盛を●6月1日
35 氷の朔日 「蛇と蚊の出るは駒込の六月」●6月1日
36 鞍馬の竹伐 山伏の験競べ●6月20日
37 夏越(の祓) 「みそぎぞ夏のしるしなりける」●6月晦日
第3章
38 七夕 星に願いを●7月7日
39 七夕の雨、七夕の水 「たとえ三粒でも降るがよい」雨を乞う習わし
40 土用の丑 鰻養生は万葉の昔から●7月20日?8月7日ころ
41 お盆 亡き人を迎える心と形●7月13?15日/8月13?15日
42 盆踊りと送り盆 お精霊さんとの過ごし方●7月15日/8月15日
43 祇園祭 祇園(天王)さんは最強の祓神●7月中
44 原爆の日 「ノーモアヒロシマ・ノーモアヒバクシャ」●8月6日・9日
45 ねぶた、竿灯 これも七夕行事●8月上旬
46 終戦記念日 「戦没者を追悼し平和を祈念する日」●8月15日
47 地蔵盆 地蔵と子ども●8月23?24日
48 重陽 菊の節句●9月9日
49 放生会 殺生の戒め●9月15日
50 敬老の日 老人を敬愛し、長寿を祝う●9月第3月曜日
51 月見 月を愛で収穫に感謝を●旧暦8月の十五夜
第4章
52 後の月 さまざまな月を祝う●旧暦9月の十三夜
53 長崎、唐津おくんち おくんちは「お九日」●10月7?9日/11月2?4日
54 神無月 神の留守●旧暦10月
55 亥の子 ぼた餅の来る日●旧暦10月初めの亥の日
56 ハロウィーン 古代ケルト人の収穫祭?●10月31日
57 酉の市 酉の市とはどんな市●11月中の酉の日
58 文化の日 明治節から「自由と平和を愛し、文化を勧める」日へ●11月3日
59 七五三 子どもなりの節目を祝う●11月上中旬
60 冠婚葬祭 行事の理解のために?
61 勤労感謝の日 「新嘗祭」の伝統●11月23日
62 神楽月 火の祭の月●旧暦11月
63 事八日 家に一つ目小僧がやって来る●12月と2月の8日の晩
64 冬至 一陽来復の日●12月22・23日ころ
65 クリスマス 幸せをもたらすものに祈りを●12月25日
66 大晦日 新年は大晦日の晩から●12月31日
67 行事と昔話 今は昔 昔は今
長沢 ヒロ子[ナガサワ ヒロコ]
著・文・その他/編集
大沢 裕[オオサワ ヒロシ]
著・文・その他
内容説明
「初午」なんの行事か知っていますか?これだけは知っておきたい日本の年中行事・祭礼。イラストを多用し、分かりやすく解説!
目次
1 1月~3月(正月―迎える心と形・1月1日~7日;初夢・書き初め―1年の計は「2日」にあり・1月2日 ほか)
2 4月~6月(エイプリルフール―道化が演じる「逆さま世界」の寓喩・4月1日;鎮花祭―「やすらい花や」と、散る花を惜しむ・4月上旬 ほか)
3 7月~9月(七夕―星に願いを・7月7日;七夕の雨、七夕の水―「たとえ三粒でも降るがよい」雨を乞う習わし ほか)
4 10月~12月(後の月―さまざまな月を祝う・旧暦9月の十三夜;長崎、唐津おくんち―おくんちは「お九日」・10月7日~9日/11月2日~4日 ほか)
著者等紹介
長沢ヒロ子[ナガサワヒロコ]
元・國學院大學日本文化研究所研究員。目白大学人間学部子ども学科非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 松浦武四郎関係文献目録