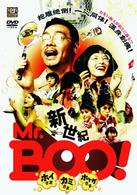内容説明
「国際法上保有・憲法上行使不可」日本的解釈の摩訶不思議。
目次
日本的バイアスの三位一体
集団安全保障と集団的自衛権
内閣法制局の不遜
憲法上、保有しているのか
日米同盟が験されるとき
小泉政権―「赤」から「黄」へ
安保法制懇のうたかた
政権交代と集団的自衛権
定義の誤り―「非同盟国」「中立国」の主張を聴け
新しい「定義」私案〔ほか〕
著者等紹介
佐瀬昌盛[サセマサモリ]
昭和9年(1934)大連生まれ。東京大学教養学部卒業、同大学院(国際関係論専攻)修了。政府交換留学生としてベルリン自由大学に留学したのち、東大助手、成蹊大学助教授を経て、防衛大学校教授。平成12年(2000)3月退官。防衛大学校名誉教授。拓殖大学海外事情研究所客員教授。専攻・国際政治(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
20
集団的自衛権を冷戦の産物視するのは誤り(37頁下段)。集団とは、2つ以上の国家が集まって、1つのまとまりをなしている状態、2つ以上の国家が、なんらかの要素を媒介として集まっていること。自衛とは、ある国家が自己を守ること。通していうと、3通りの答が出るという(53頁)。集団的自衛権に名を借りての過剰の武力行使や、武力行使の濫用は、あってはならない。日本の議論は、望遠鏡を逆から覗いているようなもので、国際的議論と歩調が合わないのは問題だ(125頁)。 2014/10/14
void
3
【★★★☆☆】旧版('01年)+加筆で1.7倍。'12年。国際法上の解釈によって、政府解釈「国際法上保有、憲法上行使不可」を批判するのが主。まあ発言の変遷を追うほど歪だよね。この本では自衛隊創設とかそこまで遡る歴史観点には欠けているが。自衛隊を違憲とする考えが強いから一顧だに値しないのかもしれないが、自然法についても、立憲主義(特にこの権力制限という観点)についても、憲法学的にみると疵が多い。2014/01/14
Shuhei Ueno
1
法律学的な論じ方が興味深い。 一点だけ、論理的にどうなのってのは、密接な関係にある国=同盟国ってのは、そうと決めつけて中立国についてまで語るのは破綻してるんじゃねえか、と思った。 実ではなくてを論理言った時に、持ってない使えないことにするのは、やはり無理筋。 海外活動のみが制限されているという整理は正しい。そういう意味でイラク戦争への参加はだめだったんだろと思う。2014/10/20
v&b
0
主張の方向や内容の妥当性に関係なく、語り口でていねいに聞く気が失せてしまった。準備作業が省略されている感が拭えない。「戦争」「敵・味方」の是非についての価値観の相違から主張が分岐し、出た結論を補強するための議論が詳細に展開されている風に感じた。ので、より遡ったそもそも論を中心にした話を見聞きしたい。資料価値はありそうだが、いかんせん(形式が)マッチョ。2015/09/12
くらぴい
0
世界的状況は、集団的自衛権が標準になっているのがみえてきてます。法制局長官が微妙な表現で言い換えてますが、国内世論の学習状況の深化に期待する感じです。2015/04/11
-

- 和書
- 僕の高校中退マニュアル