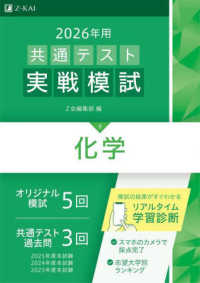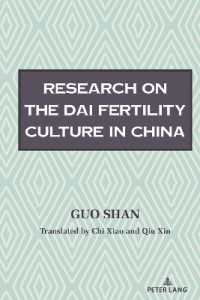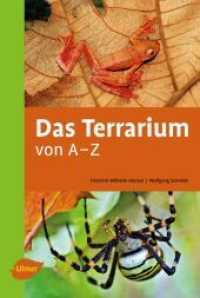内容説明
明治期、国を挙げての養蚕、製糸、絹織物の振興策が取られる。富岡製糸場の器械製糸をキーワードに、生糸、蚕種の輸出や養蚕技術の向上策など、日本版産業革命の推進力になった「絹の道への先駆け」ロマンとは!
目次
第1章 生糸が先陣になった近代産業の夜明け
第2章 渋沢栄一による近代化指導
第3章 生糸産業を支援した群馬県令・楫取素彦
第4章 生糸貿易の先覚者・中居屋重兵衛
第5章 富岡製糸場の開設と初代所長・尾高惇忠
第6章 ポール・ブリュナによる器械技術の移入
第7章 速水堅曹と富岡製糸場の民営化
第8章 生糸で横浜経済界に君臨原善三郎・富太郎
第9章 生糸産業の先駆者・星野長太郎の光と影
第10章 アメリカで成功した生糸実業家・新井領一郎
著者等紹介
志村和次郎[シムラカズジロウ]
ノンフィクション作家・歴史研究家。群馬県に生まれる。群馬県立前橋高等学校卒。1961年、同志社大学法学部卒業。経営コンサルタント(中小企業診断士)。起業支援団体・ニュービジネス機構の代表理事。1997年「明治史の研究」で文筆活動に入る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Sanchai
3
富岡製糸場等の世界遺産登録に合わせて上毛新聞が組んでいた様々な特集の1つ。 富岡製糸場が蚕糸業人材育成の拠点となっていた期間は意外と短く、その後は採算維持のためにいろいろ取組みが進められたが、それにコンパクトに触れている本として有用。また、生糸の主要輸出先が欧州から米国に変化していった経緯が、本書を読んで初めてわかった気がする。あまり読みやすい文章ではないが、深谷や群馬の人が読むと地元への愛着がわきそう。これ読んでおくと、来年の大河ドラマが面白くなりそう。2014/11/29
SK
2
どうにも文章が面白くなく。妙に保守的な臭味があるからか? 興味のあるテーマなのだが、読み飛ばしてしまった。2020/11/27
ノリ
0
日本の絹織物や製糸が世界に通用するようになったのは、明治政府や先駆者の苦労があってこそのものでした(^_^) この本の中で一番好きなのは新井良一郎です! 渡米して日本の絹織物を根付かせた開拓者です(*^^*)2014/09/13