内容説明
もうひとつの瑞穂の国から。米と箸の国は懐しさと驚きにあふれていた。豊かな米食文化の国「ベトナム」を30年にわたって食べ続けたノンフィクション。写真160点収録。米麺メニューは80種を紹介。
目次
第1章 熱帯にたなびく稲穂たち(白飯、喰ったか―コム・チャン(サパ)
桃源郷の酒―ズオ・ネップ・カム(ディエンビエンフー) ほか)
第2章 喜びも悲しみも米とともに(武骨な麺は忖度しない―フォー(ハノイ)
難民が愛した黒い麺―バイン・ダー(ハイフォン) ほか)
第3章 ベトナムご当地麺街道(一六皿の焼きそば―ミー・サオ(ハロン湾)
古都が持っている特別―ブン・ボー・フエ(フエ) ほか)
第4章 米と麺のワンダーランド(体臭と食欲がよどむ銀河鉄道―ミー・ゴイ(南北統一鉄道)
壺酒から飛び出したミスユニバース―ズオ・カン(バンメトート) ほか)
第5章 水田の恵みは国境を越えて(米が屋根でみのる豊穣―チャオ(カントー)
“南蛮”からやって来た麺―フーティユ(ソクチャン) ほか)
著者等紹介
木村聡[キムラサトル]
1965年生まれ。フォトジャーナリスト。新聞社勤務を経て94年よりフリーランス。国内外のドキュメンタリー取材を中心に活動(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
rosetta
23
南北に細長い瑞穂の国とは日本のことかと思いきや実はベトナムもそうだった。ジャポニカ、インディカと種類が違うから一概に比べられないが、それでも世界3位の米の輸出国、炊いて麺にして餅にしてライスペーパーにして、とにかくベトナムの人はお米が大好きなんだなぁ、米麺をライスペーパーに巻いてご飯と一緒に食べるとかってw。日本人にとっての味噌と醤油を合わせたような国民の味ヌク・マム(魚醤)も欠かせない。せっかく写真も沢山あるのだからキャプションつけるとか本文にリンクしてくれればいいのに。2021/01/27
アリーマ
11
ちょっとディープでマニアックなベトナム食紀行。フォーやボー、チキンライスといった日本でも一般的なベトナム料理からちょっと凝ったものまで、ベトナム食の奥にあるものを、味わい深い現地の風景とともに描き出す。写真も良い。作者のベトナム食に対する偏愛ぶりが行間からダダ漏れに流れてきて、これはまさにメシテロ。読んでいたら堪らないほどフォーやボーが食べたくなる。いつかは現地で、と言いつつ随分経ってしまったが、是非とも実現しよう、という気になった。借りた本だが手元に置きたくて買ってしまった。★★★★★2020/03/30
ろべると
7
麺の種類の豊富さで言えば、世界中でベトナムが随一ではないか?フォーが有名だが、もっとも食べられているブンも同じく米から作る麺だし、南部のフーティエとかもある。ホイアンのカオラウ、古都の辛いブン・ボー・フエ、ハノイのブン・チャー、カニ出汁のブン・リュー… 写真家である著者がベトナム各地で出会った米や麺の料理の数々。写真だけでなく文章からも、ベトナム庶民と食の生き生きとした暮らしが伝わってくる。2023/07/16
ハル
3
比較的ベトナムの田舎飯に着目したような印象がある。深刻な被害をもたらした工業廃水の事件や、貧困にあえいだ国民の話など、寂しさや世知辛さ漂う話もちょこちょこ。失礼ながら筆者の感性があまり好きではなかったけれど、ベトナム全土の食文化を多くの写真とともに知ることができた。先に読んだ「ベトナムめしの旅」との表記の重なりで既知の友人に出会ったようなうれしさを感じたり、筆者による表現の違いを味わって楽しんだ 。個人的には「ベトナムめしの〜」の方が好み。しかし、同じ分野について複数冊読むと楽しいね。2024/03/22
akanishi
2
食材、調理についての描写がみごとで、著者は料理人なのかなと思ったが、フォトジャーナリストが本業らしい。たしかに写真もステキだった。(p16)おこげをオカズに白飯を食う、(p186)鍋のシメでなく序盤から米を食う、などなど、他のベトナムグルメ本にはないものも多かった。本筋ではないのだが、(p153)バイン・チャンとアオ・チャンの連想もバカバカしくてよかった。2025/01/20
-
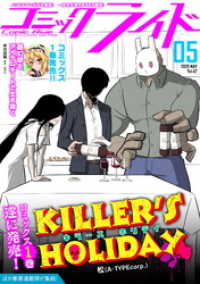
- 電子書籍
- コミックライド2020年5月号(vol…




