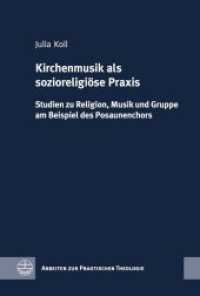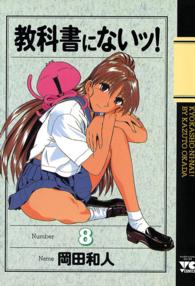内容説明
言語習得以前の思考=メタファー(隠喩)思考なくして論理も科学も発達しない。「科学」と「文学」の対立を越えて。メタファー思考と科学とをつなぐ「文学的思考」の重要性を、心理学、戦争文学、脳科学等の観点から多角的に説く。
目次
第1章 歌はいのちの力(歌は文学か;ファドの文学性;文学のクラウドはあるのか ほか)
第2章 物語は生のメタファー(神話はうそか?;物語は生命保存の武器?;物語は脳に備わっている ほか)
第3章 文学は古傷をいやす(個人物語の誕生;精神分析と文学;マザコンとカタルシス ほか)
著者等紹介
大嶋仁[オオシマヒトシ]
福岡大学名誉教授、日本比較文学会および国際比較文学会理事、からつ塾代表。福岡大学で二〇年間比較文学を教える。その前はパリ国立東洋言語文化研究所、さらにその前は南米アルゼンチン、ペルーの大学で日本思想史と日本文学史を教える。大学に入った年に大学紛争、日本を逃れてフランス留学。以来、日本語・日本文学を外から見る視点を養う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
wiki
4
「文学無用論ほどの無知、時代遅れの発想はない」と、強い語気で語る。感覚的なものを言語化していく過程が、身体感覚や心情に直結する文学にある、という「メタファー(隠喩)思考」=「言語習得以前の思考」=「文学的思考」の重要性を説く。文学に何が出来るかーー。常に議論に挙げられるこの話題は、短期的に結果を求める思考経路であるほど無用論に至りがちだと思う。しかし身体感覚のない科学は暴走する。文学を教養として身につけていれば、長期的に絶大な力を発揮すると思う。現代人よ、ビジネス書も良いが、文学を読もうじゃないか。良書。
-
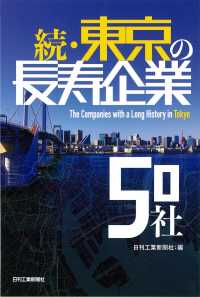
- 和書
- 続・東京の長寿企業50社