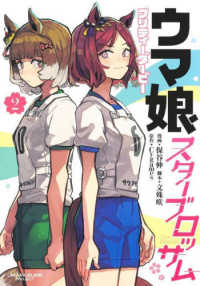出版社内容情報
国家に管理・保護されず〈定住地〉というものを持たない人々がいた。どのような事情から漂泊民(放浪・廻遊民)となり、また消滅し…漂泊民(放浪・廻遊民)はなぜ消滅してしまったのか。
かつて国家権力に管理されず、保護もうけず、自身の生き方死に方を自らの責任で決めながら〈定住地〉というものを持たない人々がいた。サンカ、家船の民、ハンセン病者、乞食という漂泊民たちである。彼らはどのような事情から漂泊民(放浪・廻遊民)となったのか、また消滅させられたのか。さらに、定住すること=国家に管理されることは本当に当たり前のことなのか。本書で著者が投げかける問題はすべての現代人に再考を迫っている。なお、本書では職人集団としての廻遊民とやむを得ず移動する放浪民とを区別している。
第1章 「サンカ」―九州山地の廻遊民
「サンカ」とはなにか/九州の「サンカ」/日本近代社会と「サンカ」
第2章 家船と「シャア」―海と陸を廻遊する人びと
「シャア」と津留の家船集落/家船のくらし/津留の習俗と生業/日本近代社会と家船
第3章 浮浪らい―放浪するハンセン病者
四国を放浪するらい者/近代の「浮浪らい」/ある放浪するらい者
第4章 ふたりの〈紀州〉―放浪する乞食たち
佐伯町の〈紀州乞食〉/清水精一ともうひとりの〈乞食紀州〉/乞食と近代日本
第5章 別府と的ケ浜事件――都市型下層社会の形成とその隠蔽
終 章 非定住から近代国家を問う
長野 浩典[ナガノ ヒロノリ]
1960(昭和35)年、熊本県南阿蘇村生まれ。熊本大(日本近現代史専攻)卒。現在高等学校教諭。著書に、『街道の日本史《国東・日田と豊前道》』『ある村の幕末・明治《「長野内匠日記」でたどる75年》』『生類供養と日本人』など。
内容説明
漂泊民(放浪・廻遊民)を受け入れられなくなった現代社会がはらむ非人間的な現象(経済格差の拡大、管理と排除の進行、競争と孤立、効率優先主義など)を見極め、寛容さが希薄になってゆく「近代国家」の淵源はどこにあるのか、そしてこれからその寛容さをどのように回復させていけばよいのか、を問いかける画期的な書。
目次
第1章 「サンカ」―九州山地の廻遊民
第2章 家船と「シャア」―海と陸を廻遊する人びと
第3章 浮浪らい―放浪するハンセン病者
第4章 ふたりの“紀州”―放浪する乞食たち
第5章 別府と的ヶ浜事件―都市型下層社会の形成とその隠蔽
終章 非定住から近代国家を問う
著者等紹介
長野浩典[ナガノヒロノリ]
1960(昭和35)年、熊本県南阿蘇村生まれ。1986(昭和61)年、熊本大学大学院文学研究科史学専攻修了(日本近現代史専攻)。現在、大分東明高等学校教諭(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
BLACK無糖好き
kuukazoo
カール
uehara