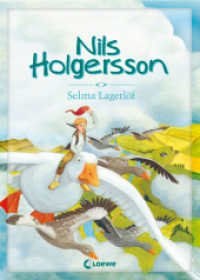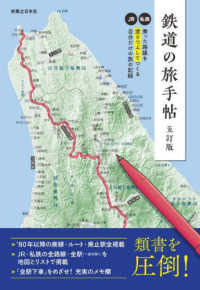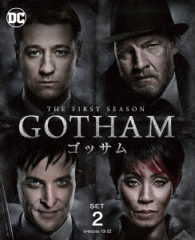内容説明
動的平衡は、古くて新しい世界観であり、機械論的・因果律的な世界観に対するアンチテーゼ、あるいはアンチドート(解毒剤)としてある。この考えに共鳴してくれた人たちとともに、世界の過去・現在・未来を動的平衡の視点から論じ合った記録。
目次
第1章 見えないものに、動的平衡は宿る(記憶とは、死に対する部分的な勝利なのです;複数の「私」を生きる―分人主義とは?;「知的生命体」が宇宙にいるのは必然か;無常の世では「揺らぐ」ことが強さである)
第2章 目に映るものは、動的平衡と寄り添う(未来の知は「昨日までの世界」に隠されている;建築にも新陳代謝する「細胞」が必要だ;「ケルトの渦巻き」は、うごめく生命そのもの;「美しい」と感じるのは、生物にとって必要だから)
著者等紹介
福岡伸一[フクオカシンイチ]
生物学者。1959年東京生まれ。京都大学卒。米国ハーバード大学医学部博士研究員、京都大学助教授などを経て、青山学院大学教授。2007年に発表した『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書)は、サントリー学芸賞および新書大賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
どんぐり
65
世界のありようを動的平衡の視点から論じ合った福岡先生の対話集。ゲストは作家のイシグロ・カズオをはじめ、平野啓一郎、作家・僧侶の玄侑宗久、『銃・病原菌・鉄』の著者ジャレド・ダイアモンド、建築家の隈研吾、日本画家の千住博など8名。それぞれ対話にしてはやや短めで、特にイシグロとの対話が記憶とアイデンティティをめぐる話だったので、もっと読みたい部分であった。それでもこのダイアローグを、動的平衡という場においてすべてが一回生の現象として生起することに重ねるなら、これはこれで面白い対話になっている。2018/05/01
yumiha
36
対談集。読みたかったのは、カズオ・イシグロとの対談。『遠い山なみの光』を書く前はミュージシャン志望だったそうで、『夜想曲集』を思い出し納得した。絶え間なく破壊され作り直される細胞のように、記憶もまた再構成を繰り返す。ここから『忘れられた巨人』へと繋がるのだらふ。他の方々との対談も、私の固定観念を揺さぶってくれたので、面白く読めた。たとえば「進化」も、「そのときどきで行ける方向へ行っただけ」と断言されて、驚いた。大河ドラマ『いだてん』のタイトル文字は、ケルトの渦巻文様「トリスケル」と全く同じだと思った。 2019/08/11
akira
21
図書館本。 福岡先生の動的平衡論を元にした各ジャンルの著名人との対談。なかなか興味深かった。「生命は動的な平衡状態である」という同論のもと、人間を取り巻くものの多くが、ある流れの中で状態として存在しているという話はおもしろい。 カズオ・イシグロ氏との印象に残るやり取り。記憶を固定したくて作家になったという同氏の作品からは、既知のような感覚にもよく遭遇する。ただ小説なのではなく、そういった要素が惹きつけるのかもしれない。 「私はとくに、ノスタルジーを掻き立てる幼少期の記憶に惹かれるんです」2018/03/25
minochan
18
東京のように作り直された町は、区画ごとに一つの町名がつく。一方、京都など昔ながらの町では、通りの両側で一つの町名がついている。生活の実態は後者のような、境界でのモノや情報のやり取りが中心だと感じた。生物もまた、構成分子そのものだけでなく、それらがどのように相互作用するかが重要だと考えさせられる。学部生のころに読んだ本書の内容をほとんど忘れていたが、今の思想や考え方、また博士論文のテーマ(タンパク質-タンパク質、タンパク質-リガンド相互作用)にまで無意識に影響を受けていたことに気がついた。2025/01/09
ヨクト
18
生物学者・福岡先生と様々な分野の方々との対談集。カズオ・イシグロ、平野啓一郎、ジャレド・ダイアモンドと錚々たる顔ぶれ。動的平衡、絶え間ない流れは生命一個体の中だけにとどまらず、地球あるいは宇宙単位で流れ続ける。イシグロさんの記憶についての話、ダイアモンド氏の世界の話が印象的だった。「私たちはいくらでも揺らいでいい、いや、むしろ揺らいだほうがいい。そう思えたら、いまよりずっと楽に、そして強く生きていける。」2014/02/09
-
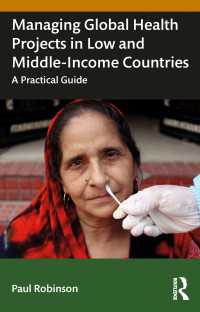
- 洋書電子書籍
- Managing Global Hea…