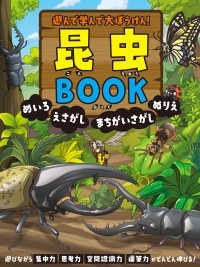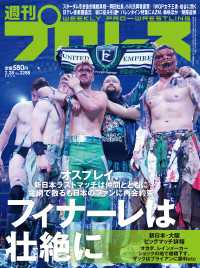内容説明
2000年、ワトソンが少年時代を過ごした南アフリカ、クニスナの森で大母(メイトリアーク)と名づけられた一頭の象が姿を消した。最後に残された象を探し、彼が向かった先は…。幼少期の不思議な体験と、アフリカに込めた思いがここに結晶する。象の魂(エレファントム)が漂う大地を舞台にした、ワトソン渾身の作品。
目次
第1章 白い象を見た少年
第2章 羊の皮を着た男
第3章 「火遊び」をした日
第4章 象たちの受難
第5章 追跡の果て
第6章 クニスナの太母
第7章 時空を超えて
著者等紹介
ワトソン,ライアル[ワトソン,ライアル][Watson,Lyall]
1939年アフリカ・モザンビーク生まれ。南アフリカ、オランダ、ドイツ、イギリス等で学問を修め、動物行動学の博士号のほか、生態学、植物学、心理学など10の学位を持つ。人間界における超常現象を収集し、「新自然学」の確立をめざす。ヨハネスブルグ動物園園長、英国国営放送(BBC)のプロデューサー、ライフサイエンス財団理事などを歴任。クジラやイルカの行動学研究も駆使し、一環して「生命」と「意識」を結ぶ神秘を追求する。1973年発表の『スーパーネイチュア』が全世界で100万部を超えるベストセラーに。本格的執筆活動に入る。2008年、永眠
福岡伸一[フクオカシンイチ]
1959年東京生まれ。京都大学卒。米国ロックフェラー大学研究員、京都大学助教授などを経て、青山学院大学理工学部化学・生命科学科教授。専門分野で論文を発表するかたわら一般向け著作・翻訳も手がける。著書に『もう牛を食べても安心か』(文春新書、科学ジャーナリスト賞)、『プリオン説はほんとうか?』(講談社ブルーバックス、講談社出版文化賞)『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書)は、ベストセラーとなり、2007年度サントリー学芸賞および、中央公論新書大賞を受賞
高橋紀子[タカハシノリコ]
翻訳家。WEB開発者。京都大学卒(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Bartleby
Sakie
ヨクト
大島ちかり
Moeko Matsuda