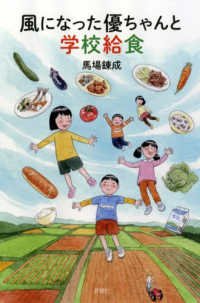- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(海外)
出版社内容情報
バウムクーヘン、木工おもちゃ、水力登山鉄道やパン屋…。
ドイツで100年の間、受け継がれてきた“ものと人々”の姿を訪ねた一冊。
社会構造や価値観が大きく変化したドイツの100年を、
人々の暮らしを支えてきた“もの”を通して振り返った一冊です。
バウムクーヘン、木工おもちゃ、水力登山鉄道やパン屋……
100年の間、受け継がれてきたものの姿、人々の想い、町の歴史を、
カラー写真と丁寧な文章で追っています。
EINLEITUNG はじめに
KAPITEL1 もの作りの100年を訪ねる
01ザイフェンの木工おもちゃ工房
02ベルリン名物になった福祉作業所のブラシ
03骨董品のようなスリッパ工房
KOLUMNE_1 街中に残る100年もの
KAPITEL2 お菓子作りの100年を訪ねる
01バウムクーヘンの老舗カフェ
02ペッファークーヘンを焼き続けた街
03ドレスデンに帰ってきたシュトレン
KOLUMNE_2 100年前の面影を残す街
KAPITEL3 エコの源流を訪ねる
01元祖自然レフォームハウス
02水力発電のクリーニング屋
03優雅な街に残る水力登山鉄道
KOLUMNE_3 家賃無料、築100年の家に住んでくれる人求む!
KAPITEL4 100年の歳月を見つめて
01戦災で焼け残ったダンスホール
02統合と分断を経験したベルリンの地下鉄
03100年の間に変化したもの
KAPITEL5 ドイツ人の食卓
01市場でドイツ人の食生活を観察する
02ドイツ人の食卓に欠かせないパン
03肉屋でソーセージを食べる
KOLUMNE_4 100年近い歳月を生きて
ドイツ/ベルリン地図
NACHWORT あとがき
CHRONOLOGIE&VERWEISUNGEN 年表と参考文献
【著者からのコメント】
今からさかのぼるドイツの100年は、2度の世界大戦とナチスの台頭、
東西分断と再統合を経験した激動の100年でした。
社会構造やものごとの価値観が大きく変化する中で、人々はどのように生きてきたのか。
ドイツの市民生活の中にあって100年生き抜いてきた“もの”に焦点を当てることで、
100年という時間を感じてみたいと思いました。~「はじめに」より抜粋
【著者紹介】
見市 知(Tomo Miichi)
ライター。ドイツ在住。著書に『ベルリン 東ドイツをたどる旅』、
『ドイツ クリスマスマーケットめぐり』(産業編集センター)がある。
内容説明
バウムクーヘン、水力登山鉄道、木工おもちゃ、パン屋…100年の間、受け継がれてきた“ものと人々”の姿。社会構造や価値観が大きく変化したドイツの100年を、人々の暮らしを支えてきたものを通して振り返った一冊。
目次
1 もの作りの100年を訪ねる(ザイフェンの木工おもちゃ工房;ベルリン名物になった福祉作業所のブラシ;骨董品のようなスリッパ工房)
2 お菓子作りの100年を訪ねる(バウムクーヘンの老舗カフェ;ペッファークーヘンを焼き続けた町;ドレスデンに帰ってきたシュトレン)
3 エコの源流を訪ねる(元祖自然レフォームハウス;水力発電のクリーニング屋;優雅な街に残る水力登山鉄道)
4 100年の歳月を見つめて(戦災で焼け残ったダンスホール;統合と分断を経験したベルリンの地下鉄;100年の間に変化したもの)
5 ドイツ人の食卓(市場でドイツ人の食生活を観察する;ドイツ人の食卓に欠かせないパン;肉屋でソーセージを食べる)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かずぼう
ykshzk(虎猫図案房)
べべっち
ZEPPELIN
きょう