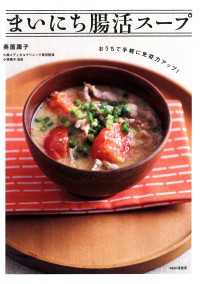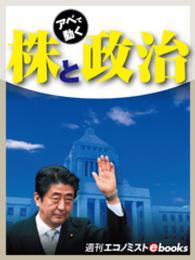出版社内容情報
◎認知症、軽度認知障害(MCI)予防に効果的!
「認知症予防会話の専門家」が最新の研究に基づいて考案した
「脳が長持ちする会話」を実践して一生使える脳になる!
<こんな悩みありませんか?>
「アレ」「ソレ」が増えた。
話の途中でよくつまる。
ものごとの説明がうまくできない。
忘れ物の頻度が高くなってきた。
作業の処理速度が落ちた。
深刻ではないけれど、少し気がかりなことが増えていませんか?
人生100年時代のいま、かかりたくない病気、そして親にかかってほしくない病気と言えば、認知症でしょう。
脳の認知機能を保つ、つまり脳を長持ちさせるポイントに「会話」があります。
脳を活用する実践的な会話を知って予防・対策をすれば、脳を長持ちさせることができるのです!
内容説明
認知症予防の新常識。40代、50代から始められて、60代以降も日常に簡単に取り入れられる、会話のコツ19、生活習慣16。脳の健康度は「会話」から分かる。
目次
第1章 今から始める脳の老化対策(人生100年時代、最大の不安が「脳の老化」;会話で脳の働きを計測できる ほか)
第2章 「六つの工夫」で脳が長持ち(知的活動と社会的交流で長持ち脳を創る;「三つの認知機能」を活用しよう ほか)
第3章 実践編 日常会話で脳を活用する(「この俳優さんの名前なんだっけ?」が増えたら『最近の話』をする;会話が億劫に感じられるときは『新しい体験を覚える』ことを心がける ほか)
第4章 実践編 脳の健康を保つ生活術(生活の工夫で、脳や身体が老化しても認知機能低下を遅らせる“認知的アプローチ編”;生活の工夫で、脳や身体の老化を遅らせる“生理的アプローチ編”;周りの人の脳の健康を保つ工夫)
著者等紹介
大武美保子[オオタケミホコ]
1975年東京生まれ。ロボット工学者、認知症予防研究者、博士(工学)(東京大学)。2児の母。認知症を予防する会話支援手法「共想法」を開発、理化学研究所革新知能統合研究センター・チームリーダーとして、認知症予防のためのAI・ロボット研究を、チームメンバーと共に推進。同時に、創設したNPO法人ほのぼの研究所の代表理事・所長を務める。科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞、人工知能学会現場イノベーション賞、ドコモ・モバイル・サイエンス賞「社会科学部門」選考委員特別賞等受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パフちゃん@かのん変更
てん06
まいさん
Humbaba
book mom