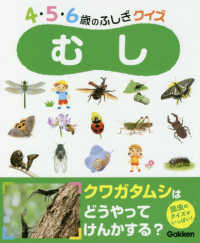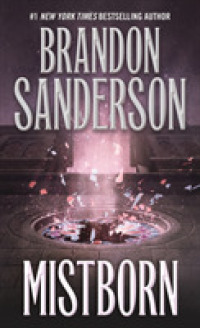- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 絵画・作品集
- > 浮世絵・絵巻・日本画
内容説明
山は鳴動し、馬が話し、龍が飛ぶ。将軍は虹を飲み込み、百鬼が練り歩き、高僧は奇跡をおこす…中世はふしぎな出来事がたくさんおきた時代でした。この本はそんなふしぎの背景を美しい挿絵とともに解説。激動の中世が体感できるまさに、現代版「絵巻」です。
目次
妖の章(北野天満宮の怪鳥;室町御所の妖物;髪切りの怪 ほか)
怪の章(金花銀花;聖地からの警告;虹立つ ほか)
化の章(釜鳴り;竹林の女;虹を飲む夢 ほか)
著者等紹介
西山克[ニシヤママサル]
東京都生まれ。京都大学大学院博士課程単位取得。関西学院大学文学部教授。東アジア恠異学会前代表
北村さゆり[キタムラサユリ]
静岡県生まれ。多摩美術大学大学院美術研究科修了。日本画家として、また2015‐16年には日本経済新聞で新聞小説(宮部みゆき「迷いの旅篭」)の挿絵を担当するなど、幅広く活躍中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Willie the Wildcat
70
表題に負けない本著の”つくり”にまず驚かされる。構成は、妖・怪・化の3章立て。「妖」の『妖怪絵の誕生』の災害記録説に腹落ちし、「怪」の『中世のスターウォーズ』の言い得て妙な解説に納得感、そして「化」からは文字通り化身の『法然ビーム』は奇跡!?豊富な文献と、そこに見え隠れする歴史的思惑。更に興味を掻き立てる北村氏の挿絵。お気に入りの画を1点だけあげるなら狐好きの私は、迷わず『摂関家と狐』を選択。巻末の『中世ふしぎ地図』、思わず見入ってしまう。故国の深み、考えただけでも楽しい。2023/06/06
天の川
46
変形縦長の本に見えて、表紙を開くと横長の不思議な本。最初のページに「網野義彦さんとの思い出に」と書かれているように中世に関するかなり詳しい内容。1つのテーマで見開き2ページの文章、次の2ページで北村さゆりさんの絵巻物のようなイラスト。語り口はエッセイのようで読み易いが、一つ一つ中世の史料を紹介されていて、中世の人々がどのような生活を送り、怪異についてどのように捉えていたかがわかって面白い。ゆっくり時間をかけて読みたい。2022/10/22
よこたん
44
“ひげのあるおんな? いやおんなにみえてじつはおとこ あたしはかまの怪をしずめるの” 釜鳴りを鎮めるのは、女装の男巫女。これが「オカマ」のルーツとか。えっ、本当? 凝ったつくりの本で、頁を捲るのが楽しかった。ゆるくてかわいらしい絵巻のようで、所々でぞわりとする要素も見え隠れ。何だか虹がこわくなってしまった。妖しげな出来事は、日常といつも隣合わせで、みんなそれに名前をつけて、納得しようとしていたのだろうか。高僧であることの奇蹟を伝える「法然ビーム」、眼からビューンと光を放つって、すごいけどこれは笑えた。2022/05/26
moonlight
28
装丁が凝っていて、頁を開くと横に長く確かに巻物を広げたよう。一話ごとに美しい絵が全面に描かれてとても楽しい。いついつ、こんな不思議なことがありましたとさ、だけではなく時代背景の説明があるので理解が深まる。百鬼夜行についての考察、釜鳴りとオカマの関連性についての説が面白い。2024/03/10
ゆーり
20
装丁が変わっていて、表紙を横にして横長になったページを横に開いていく。まるで丸めない絵巻物のよう。見開き1ページのテキストの次のページには、北村さゆり氏の水彩画。絵だけ見て想像するのも楽しいし、読んだ後なら不思議な絵もストンとおちる。話は平安~南北朝時代の怪異談のネタバレ?のような。でも神仏への信仰が非日常的な事象への対抗策しかなかった、中世代を生きる人にとっては仕方なかった。ところで「オカマ」の語源であろうと思われる「釜鳴り」釜鳴りを起こすといわれた「婆女」を鎮めるのは→2021/11/27
-

- 洋書
- YVES DANA