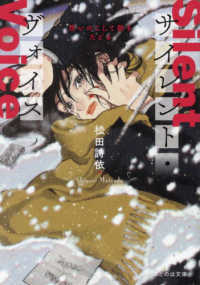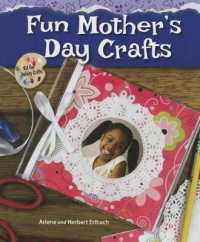内容説明
日々の習慣をほんの少し変えれば、しなやかな心と身体をつくることができる。江戸時代の大ベストセラーに学び、上機嫌に生きよう。五十の金言。
目次
第1章 生きる力―養生の基本(養生とは人が正しく生きる道;身体を養うテクニック ほか)
第2章 飲食の心得―何をどう食べるか(バランスのとれた食べ方で健康は決まる;“ついで歩き”が身を助ける ほか)
第3章 日々是好日―心をととのえる(自分の幸せの基準を持つ;自分への「見切り力」をつけよう ほか)
第4章 健康配慮社会の到来―身体をととのえる(自分の身体に合った朝の行動パターンを決める;元気の収支決算を考える ほか)
第5章 年を重ねるほど「ほぐれる」生き方―人生の楽しみ(よく生きるには、よく働きよく学べ;正しい三楽 ほか)
著者等紹介
齋藤孝[サイトウタカシ]
明治大学文学部教授。1960年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業。同大学院教育学研究科博士課程を経て現職。専門は、教育学、身体論、コミュニケーション技法(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tomoko
35
貝原益軒『養生訓』を齋藤氏が今風に解説。基本は江戸時代も今も同じなのかな。心は静かに、身体は動かす。ほどほどが肝心。食事は楽しく腹八分。日日是好日。深呼吸。考えすぎず気持ちを落ちつける。声を出して笑う。どれも難しいことではない。肩の力を抜いて、ほどほどに頑張ろう!2022/05/06
シナモン
22
図書館本。江戸時代に貝原益軒が書いた「養生訓」を齋藤孝さんが現代の人にも分かりやすく解説したもの。やはり食が基本なのか、食事に関する事が多いが日々の生活から精神論まで具体的に分かりやすく書かれている。健康法の基本的なことは江戸時代も現代もそう変わりはない。何事もほどほどに、身体を良く動かし、体の循環を良くする事が大切。「口から出入りする食べ物と言葉に気を使おう」が印象に残った。健康で長生きの先にある人生の楽しみについても書かれているのがいいなと思った。2019/03/08
太田青磁
11
「恣の一字をさりて、忍の一字を守るべし」厳しいことが書いてあるようで、ほどほどで長生きするための本。腹八分目は大切。「酒は微酔にのみ、半酣をかぎりとすべし」これができたらきっと健康になれる気がする。「憂いて食すべからず。食して憂うべからず」まずはここから、楽しく食べる。「災いは口よりいで、病は口より入るといえり。口の出しいれ常に慎むべし」余計なことは腹に収めよう。「目に精神ある人は寿し」メヂカラをきたえるべし。「要事なくんば、開くべからず」いらない情報は遠ざけよう。「呼吸は人の生気也」深呼吸心がけよう。2012/08/17
朔ちゃん
7
貝原益軒「養生訓」を、齋藤孝先生が、現代風にかみくだいて丁寧に解説。理にかなっていてすごく参考になった。「草木を手入れするように身体も手入れする」。何事もほどほどに。取り越し苦労をしないよう、呼吸を深くして、身体を動かす。温かいお茶を飲み、お風呂でも身体を温めよう。2022/02/19
telephone
3
ほどほどにバランスよく生きていきたいものだ。2016/11/03