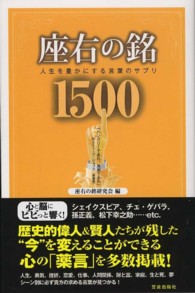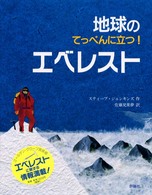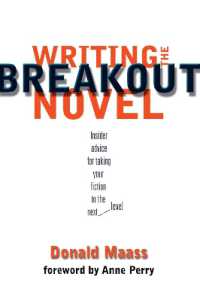内容説明
あのとき「日本人」を発見した。元ウクライナ大使だからこそ書ける日本論。
目次
はじめに 「日本」という感動が国難を乗り越える
第1章 なぜ日本は世界から尊敬されるのか(東日本大震災で見えた日本;貧しくても高貴な日本人 ほか)
第2章 世界をリードした日本外交の歴史(外交に無関心な国民;日本式外交の原点 ほか)
第3章 国難を克服する日本の力(芥川龍之介が描く日本文化の強さ;キリスト教文明の破壊する力 ほか)
第4章 日本が世界にできること(新帝国主義の時代;核心は中国に対する贖罪意識だ ほか)
著者等紹介
馬渕睦夫[マブチムツオ]
元駐ウクライナ兼モルドバ大使。前防衛大学校教授。1946年京都府に生まれる。京都大学法学部3年在学中に外務公務員採用上級試験に合格し、1968年外務省入省。1971年研修先のイギリス・ケンブリッジ大学経済学部卒業。外務本省では、国際連合局社会協力課長、文化交流部文化第一課長等を歴任後、東京都外務長、(財)国際開発高等教育機構専務理事を務めた。在外では、イギリス、インド、ソ連、ニューヨーク、EC日本政府代表部、イスラエル、タイに勤務。2000年駐キューバ大使、2005年駐ウクライナ兼モルドバ大使を経て、2008年11月外務省退官。同月防衛大学校教授に就任し、2011年3月定年退職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
T坊主
3
外務省はチャイナスクールとかあまりよい印象がありませんが、馬淵氏のような立派な見識を持たれた方もいるのだなと感じた。非常によく日本の事を思われ、研究されていて日本が今日の状況になった原因は日本人の”作り変え力”が明治維新から現在に至るまで、日本化する事ができないでいる。TPPも移民政策をそうする事を議論する前に、日本精神である”和”と”共生”を再構築すべきであると。大いに読み応えがあった。経済市場主義ではない生き方をこれから模索すべきではないか。今は平成の開国ではなく”鎖国”すべきと。2013/01/18
ぷれば
2
長く外務省に勤務し、イギリス、インド、ソ連、NY、EC、イスラエル、タイならびにキューバ・ウクライナ兼モルドバ大使を歴任した著者が、各国との外交を通じて、知り得た貴重な日本国再生のヒントがあふれている。中でも、歴史上幾たびと襲われた国難を乗りこえた日本の力「造り変える力」は、興味深い。歴史に醸成された伝統文化の力を今こそ見直したい。2015/04/19
草生やすな
1
さらっと読めた本 「つくりかえるちから」が日本を豊かにしてきたのかな。 他の国の文化も技術も日本に吸収され、日本的なものに作りかえられてしまう。何が日本人にそうさせたのだろうか?やっぱ神道なんかなぁ〜。 科学技術は勝手がちがうようで、土着化は困難かな?科学に日本がつくりかえられそうやん!2014/01/06
marusan
0
元ウクライナ大使も務めた外交官という経歴とYouTubeで陰謀論など過激な発言をされている方なので興味を持って図書館で借りて読んだ。約10年前の東日本代震災後に書かれた本なので今のウクライナやソ連のことは予想もしておらず平凡な内容。決して過激な人ではない、この後に人が変わったのか。ユダヤ教、イスラム教、キリスト教、仏教に共通する、隣人を愛する心があれば世の中から争いは無くなるのでないかとの主張?には共感。先ほどの主張と矛盾するが、キリスト教は破壊する力、日本の仏教は作り変える力との主張にも納得させられた。2022/05/29
-

- 和書
- ひきざん <VHS>