内容説明
『論語』の研究、すなわち注釈は漢代から始まり、その成果は魏の何晏(190‐249)『論語集解』にまとめられ、また300年後にはそれらも含め新たな研究を集約した梁の皇侃(488‐545)『論語義疏』が作られた。両注釈は南宋の朱憙の新注に対し古注と呼ばれた。ところが、『論語集解』から『論語義疏』に至る六朝期は注釈書が散逸し、ほとんど研究されてこなかった。著者は長年従事してきた皇侃『義疏』の研究成果に基づき、この300年間の論語注釈史を『義疏』の精査により明らかにする。皇侃は、何晏『集解』によりながらも、その解釈の一義性に疑問を抱き、自らの『義疏』では多義性を重んじて、『集解』以後の論語説を可能な限り網羅的に採り上げ、『集解』に基づく解釈である「本解」と、それとは異なる解釈「別解」とによって構成した。著者は、その中から六朝時代の論語注釈家39人を選び出し、魏、晋、宋、斉、梁、および生没年不明の注釈家に分けて時代順に配列し、注釈家の履歴、その論語説の紹介と検討、さらに問題点の指摘を行う。日常的な言葉による注釈や、その語句の生まれた社会的歴史的状況を考慮して論じる注釈など、多様な注釈が列挙され分析される。最後に資料編では、各論語説の原文を整理・対校した上で掲載し、基礎資料を提供する。紀元前から現代まで2000年以上に渡る『論語』解釈史を辿る本書は、論語注釈史研究の基礎を築くとともに中国古典学の醍醐味を伝えてやまない意義深い業績である。
目次
序章 六朝論語注釈史研究の試み
第1章 魏の論語注釈家
第2章 晋の論語注釈家
第3章 宋の論語注釈家
第4章 南斉の論語注釈家
第5章 梁の論語注釈家
第6章 生卒時期を明らかにしない論語注釈家
著者等紹介
高橋均[タカハシヒトシ]
1936年3月、神奈川県に生まれる。東京教育大学文学部文学科(漢文学専攻)卒業、同大学院文学研究科(中国古典学専攻)博士課程単位取得退学。日中学院講師、東京教育大学文学部助手、鹿児島大学教育学部助教授、東京外国語大学外国語学部教授、大妻女子大学短期大学部教授を経て、東京外国語大学名誉教授、大妻女子大学短期大学部名誉教授。博士(文学・筑波大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
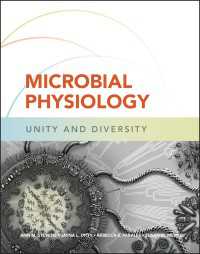
- 洋書電子書籍
- 微生物生理学:統一性と多様性(アメリカ…
-
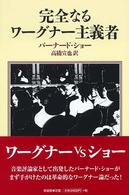
- 和書
- 完全なるワーグナー主義者






