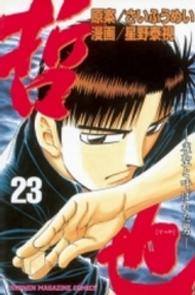出版社内容情報
文化文政期,茶道は広く庶民の間にも普及したが,作法儀礼を重視し,茶器,茶室の豪華さや奇抜さを競う風潮をも盛んにした。そのような茶道のあり方に憤り,寂庵宗澤は『禅茶録』(1828年)を著した。この書は柳宗悦をして「凡ての茶人の座右に置くべき名著だ」と言わしめた古典的作品である。
禅仏教を基盤に形成された茶道は,我執を捨て本来の自己に向きあう自己覚醒の道である。主人と客の自在な交流,露地としての茶室,清浄心を器とする茶器,不自由を不自由としない侘び,調和を超える数奇,禅と茶は体と用であり二つで一つ,といった茶道が禅の精神に裏付けられている多様な姿を見事に描き,読む者に深い感銘を与える。
本書は,多くの仏教用語で表現された「禅茶一味」の内容を理解しやすいように原文の大意を平明な現代語に訳出,原文と英訳も添えたことで,日本文化を再発見し,さらに世界へ紹介する書ともなった。茶道に関心をもつ人々にとってはまさに導きの書となろう。
序(倉澤行洋)
1 茶事は禅道を宗とする事
2 茶事修行の事
3 茶の意の事
4 禅茶の器の事
5 侘びの事
6 茶事変化の事
7 数寄の事
8 露地の事
9 体用の事
10 無賓主の茶の事
『禅茶録』原文
あとがき(吉野白雲)
参考文献
英訳
寂庵宗澤[ジャクアンソウタク]
著・文・その他
吉野白雲[ヨシノハクウン]
監修/翻訳
吉野亜湖[ヨシノアコ]
翻訳
ショーン・バーク[ショーン バーク]
翻訳
内容説明
本書は、多くの仏教用語で表現された「禅茶一味」の内容を理解しやすいように原文の大意を平明な現代語に訳出、原文と英訳も添えたことで、日本文化を再発見し、さらに世界へ紹介する。茶道に関心をもつ人々にとってはまさに導きの書。
目次
1 茶事は禅道を宗とする事
2 茶事修行の事
3 茶の意の事
4禅茶の器の事
5 侘びの事
6 茶事変化の事
7 数奇の事
8 露地の事
9 体用の事
10 無賓主の茶の事
著者等紹介
吉野白雲[ヨシノハクウン]
日本茶道塾塾長。茶道宗家にて内弟子修行後、流派にこだわらずに広く日本茶文化を伝える日本茶道塾を設立。海外向け茶道通信講座や茶道インストラクター制度などを創設するなど国際交流活動も積極的に取り組んでいる
吉野亜湖[ヨシノアコ]
日本茶道塾、茶道講師。静岡大学非常勤講師。静岡大学大学院卒(文学修士)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひめぴょん