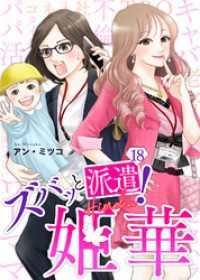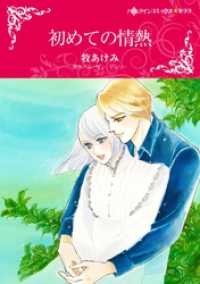感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
内島菫
21
カントの崇高論に、後にヘーゲルが練り上げた弁証法の萌芽がみられるという指摘は、弁証法の二項対立や止揚の部分よりも、否定の契機というものが釣り上げる釣果の大きさに目を向けさせる。カントの美的なものも崇高なものも、さらにはデリダの「決定の思考」も、自身から逃れ、自身の外側へ向かい、自身を内側から突き崩す契機をも含んでいる。これは一種のトートロジー的な環のようでもあるが、実際はせり上がり突き上げる螺旋を描く。2019/11/22
きつね
9
Ⅰ部・Ⅱ部を非常に面白く読んだ。とくに判断力批判を美学システムとして読もうとするとヘーゲル的思考になってしまうが、果たしてそう理解するだけでいいのか、という論理展開の仕方が小気味よい。Ⅱ部で(カントから離陸して)提示される「吐き気」「不定型なもの」「パラサブライム」といった概念がⅢ部にどう活かされるのか理解できず、Ⅲ部がどこか既視感のあるデリダ論に収束してしまうように(少なくとも、門外漢の私の理解力においては)見えた。Ⅲ部の問いをもう一度デリダ美学(?)に投げ返してもらえると文学研究者としては助かる所。2014/02/03
こややし
5
熊野純彦の「カント」読んだ流れで購入。カントの『判断力批判』が、20世紀の政治哲学において大きな問題であったことがよく分かり、面白かった。カントの趣味判断の検討から、アーレントが「政治的判断力」を引き出し、そうした政治的判断の実践が、ハーバーマスの相互理解のプロセスとして描く生活世界にも通じる公共領域を開くとしたこと。一方、同じ判断力批判の崇高論を根拠にリオタールは、そうした共同性に抵抗し、ナンシー、ブランショの共通性なき共同体論への回路が開く。2017/03/16
じょに
5
半年に1冊くらいある、知的好奇心がいい感じに触発され、且つ勉強になる本。宮崎論文は何本か読んだことがあったものの、SITE ZEROのは読んだことなかったので、良かった。カント『判断力批判』の判断力と趣味判断、美と崇高の分析から、リオタールとアレントを経て、デリダの『友愛のポリティクス』へ、みたいな感じ。レーヴィットのシュミット批判は知らなかった。勉強になった。デリダとカント『判断力批判』は『来たるべきデリダ』でコーネルが言及してるのよね(←さっき確認)。サクサク読ませる文章なのもよし。ただ、高かった。。2009/07/17