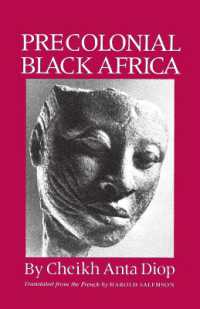内容説明
『論語』の最古の形はいかなるものか。孔子の活動や孔子学団の実態はどのようであったか。それらの考察を通して二千年以上にわたり中国社会の基盤を支えてきた儒学思想の核心に迫る。『論語』の成立に関して後世の資料や孔子の言葉自身にも信用できないものがあるなど、論語を取り巻く複雑な構造が明かされ、『孟子』については孟子思想の中心にある仁義概念の成立と漢代にかけて古代史が固定される以前の実情や抹殺された古代史について戦国中期の事情を伝える貴重な情報源であることが明らかにされる。経学前史では左氏伝、孟子、筍子などを通し『詩』『書』が固定される以前の実情を考察、経書のはらむ問題点を指摘する。また天人相関説と陰陽配当論では災異説の実際と陰陽の対応について考察する。さらに『漢書』に見られる“故事”が当時の官僚の行動基準に影響を与え、『春秋』とは異なる処罰の基準であることを示す。
目次
『論語』考索
孔子の主君と活躍
儒家学団の分派
儒家学団の分派―曾子学派攷
三年之喪攷―『論語』成立時期試探一則
孟子“仁義”説成立攷
『孟子』所見古史攷
郭店楚簡緇衣篇考索
経学前史(一)『左氏伝』所見『詩』『書』攷
経学前史(二)『筍子』『孟子』等所見『詩』『書』攷〔ほか〕
著者等紹介
沢田多喜男[サワダタキオ]
1932年3月東京都に生まれる。1958年東北大学文学部中国哲学科卒業。1963年東北大学比較文化研究施設助手、1969年東海大学講師、助教授を経て教授。1981年千葉大学人文学部教授、文学部教授。現在千葉大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
-
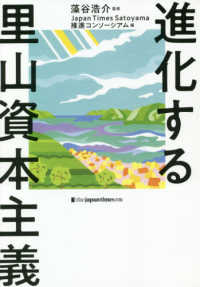
- 和書
- 進化する里山資本主義