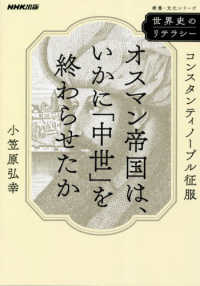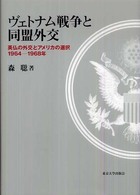内容説明
勉強会、講演会、セミナー、イベント、ワークショップ…「わくわく感」をつくる技法。知がめぐり、人がつながる場のデザイン。
目次
第1章 ルポ ラーニングバー・エクスペリエンス
第2章 ラーニングバーの誕生前夜
第3章 メイキング・オブ・ラーニングバー 当日までになすべきこと
第4章 メイキング・オブ・ラーニングバー 開催日当日
第5章 ラーニングバーから生まれた変化
第6章 他者の目から見たラーニングバー
最終章 学ぶことの意味、そして未来へ
著者等紹介
中原淳[ナカハラジュン]
東京大学大学総合教育研究センター准教授。東京大学大学院・学際情報学府准教授(兼任)。北海道旭川市生まれ。東京大学教育学部卒業、大阪大学大学院・人間科学研究科、米国・マサチューセッツ工科大学客員研究員等を経て、二〇〇六年より現職。大阪大学博士。専門は経営学習論、組織行動論。「大人の学びを科学する」をテーマに、企業・組織における人々の成長・コミュニケーション・リーダーシップについて研究している。働く大人の学びに関する公開研究会「ラーニングバー」を含め、各種のワークショップをプロデュース(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。