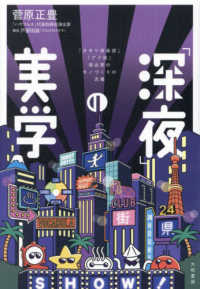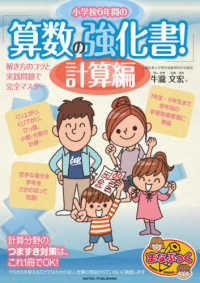著者等紹介
ヴァルザー,ローベルト[ヴァルザー,ローベルト] [Walser,Robert]
1878‐1956年。ドイツ語圏スイスの散文作家。長編小説の他、多数の散文小品・詩・戯曲を発表。1933年にヘリザウの精神療養施設に入所して以降は筆を断ち、1956年のクリスマスの朝、散歩中に心臓発作で死亡
若林恵[ワカバヤシメグミ]
東京生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程中退。現在、東京学芸大学教育学部准教授。専門はドイツ語圏文学・文化(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まふ
106
掲題作品(ヤーコプ・フォン・グンテン)のみ読む。「将来誰かに従属するために忍耐と服従しか教えない学院」にはベンヤメンタ学長とその妹のリーザしかいない。物語はヤーコブのモノローグで様々な感想が述べられて行く。そのうちに同級生が徐々に減っていき、リーザ先生も亡くなり、学長との二人だけになる…。「従僕になるためだけの生徒が数人しかいない学校」という設定も学長もリーゼも、何やらカフカの世界を思い起こさせる実存的な、不思議な作品だった。G679/1000。2025/01/07
春ドーナツ
17
「今日はこれで書くのをやめなければならない。僕は書くことに心を奪われてしまう。手に負えなくなる。文字がきらきら輝いて、目の前で踊っている」(95頁)。ちびた鉛筆とお手製のメモ帳をいつもポケットに忍ばせて、息を吸って吐くように、林間の散策の歩を止めては極小の文字で何かを書きつけるヴァルザーさんを彷彿とさせる文章だと思う。意識は絶えず更新される。5分前に私は何を考えていたのだろうか。思い出せない。氏の文章の数行前も思い出せない。小説というよりも一人の人間の「思考のドキュメント」といった感触を得る。2018/09/01
三柴ゆよし
13
「ヤーコプ・フォン・グンテン」。これほど空っぽですがすがしく、朗らかな小説があるだろうか。小説の舞台は従僕になるための学校だが、語り手ヤーコプはのっけからこう宣う。この学校で学ぶべきことは、ほとんどなにもない、と。つまり彼は従僕にすらならない。むしろ何者にもなろうとしない。どんどん小さくなって、しまいには<まんまるの零>になってしまいたいというヤーコプの願望は、そのままヴァルザー本人の生にもあてはまる。同じく小さくなっちゃう系小説の大傑作、ゴンブロ―ヴィッチ『フェルディドゥルケ』の対極に位置する作品だ。2020/09/01
rinakko
9
『鄙の宿』が本当に素晴らしく、これはもうヴァルザー読まねば…!と居ても立ってもいられず手に取った。3から読んだのは、「ヤーコプ・フォン・グンテン」お目当て。話の舞台は、ひたすら忍耐と服従を叩き込む為の授業を行うベンヤメンタ学院、語り手ヤーコプは寄宿生の一人である。良家の出身にも関わらず順応していく彼には、既に己自身が謎になってしまう…。何から何まで頗る奇妙で面白い。「フリッツ・コハーの作文集」も凄くよかった。誰にも何にも繋ぎ止められない稀有な魂の、わかり難くて不思議な明るさに強く引きつけられてやまなかった2014/04/06
ルーシー
4
ヴァルザーの小説の『言葉と思考が溢れて止まらない』という感じがクセになる。2020/11/25
-
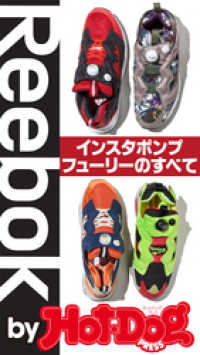
- 電子書籍
- by Hot-Dog PRESS Re…
-

- 電子書籍
- by Hot-Dog PRESS いけ…