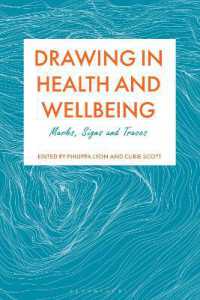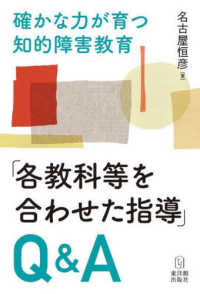内容説明
「銀の時代」最後の詩人・アルセーニーの言葉の延長線上に拡がっていた世界こそ、まさに息子アンドレイ・タルコフスキーの映像作品の原風景そのものなのだ。
著者等紹介
タルコフスキー,アルセーニー[タルコフスキー,アルセーニー][Тарковской,Арсеньевны]
1907~1989。エリサヴェトグラード生まれ。1920年代にモスクワの高等文学コースで学び、新聞やラジオの仕事に携わる。第二次大戦中に従軍記者として前線に赴いたが、負傷して片足を失う。1946年、印刷準備の進んでいた彼の最初の詩集は、いわゆる「ジダーノフ批判」の影響で頓挫、ようやく1962年に詩集『雪が降るまえに』が刊行された。十九世紀ロシアの詩人チュッチェフやフェートの伝統を受け継ぎながら、アフマートヴァら二十世紀のアクメイズム詩人たちとも近い詩風を持つ。また、カフカースや中央アジアの諸民族の詩の翻訳者としても知られている
坂庭淳史[サカニワアツシ]
1972~。東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。早稲田大学文学部助手を経て、現在、早稲田大学文学学術院、専修大学経済学部非常勤講師。専攻はフョードル・チュッチェフを中心とする十九世紀ロシア詩・思想、比較文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nina
14
アルセーニー19歳から71歳までの詩を収録。年代でいうと1926年から78年まで。世界中を巻き込んだ大きな戦争をはさんでソビエト激動の時代に生きた彼は、兄や父、青年時代想いを寄せた女性、敬愛していた閨秀詩人、そして息子アンドレイなど、幼い頃から晩年まで親しい人々の死に立ち会い、彼自身も戦争で片足を失い生死の境をさまよった。彼の作品の多くはそういった人々への想いと愛する人を失う悲しみが直接的または間接的に織り込まれている。そしてその悲しみをもってしても失うことのないロシアという大地への情熱とノスタルジアも。2014/01/22
tow
8
詩はよく分からないのだけど、生きた時代が飛び込んでくるような感覚。2016/09/07
MO
7
蝋燭/黄色い舌を揺らめかせ 蝋燭がゆっくり溶けて流れゆく。そうやって僕たち二人も生きているね、魂は燃え、肉体は融けてゆく。2022/02/24
吟遊
5
彼の言葉遣いが好き。白い、白い日もよかったし。2015/12/15
宵子
1
sknw先生が訳した本の一つ。 アンドレイ・タルコフスキーは息子で、ロシアの有名な映画監督である。「鏡」や「ノスタルジア」には、父の詩や詩について見られる。 実はこの本を読むまでは、叙情詩は嫌いであったが、それを変えてしまった本である。日本は詩人の地位が西洋と比べたら低いしね…。 内容はロシア的(ウクライナ的)なモチーフが多く、冷たく暗い印象と暖かさを受ける。2010/06/10
-

- 洋書
- The Psalms
-
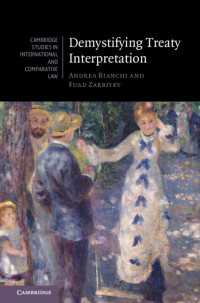
- 洋書電子書籍
-
条約解釈の脱神話化
Demyst…