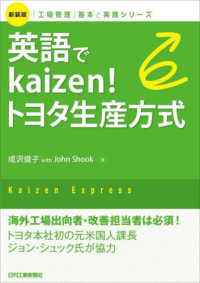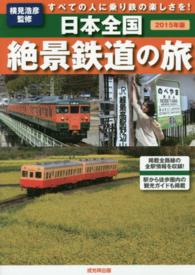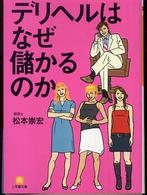内容説明
名監察医が暴き出す!自殺死体に隠された真実…2万体の“死体”を検死した監察医の最後の提言。
目次
第1章 子どもは決して“自殺”しない(いじめられっ子の自殺;遊び感覚のいじめっ子;学校・教育委員会の対応;警察の対応;いじめと自殺の因果関係;いじめと社会)
第2章 自殺はどうしてなくならないのか?(ストレス社会の日本;社会に殺された人々;老人の自殺)
第3章 「自殺は他殺だ」と私が言い続ける理由(言葉の暴力;自殺の現実)
第4章 死の真相を突き止めるために…(監察医の仕事;ある殺人事件の鑑定;自殺と他殺の見分け方;検視制度の見直し)
著者等紹介
上野正彦[ウエノマサヒコ]
1929年、茨城県生まれ。元東京都監察医務院長・医学博士。東邦医科大学卒業後、日本大学医学部法医学教室に入る。59年、東京都監察医務院の監察医となり、84年から同院長となる。89年の退官後に執筆した初の著書『死体は語る』(時事通信社)が、65万部を超える大ベストセラーとなる。現在は、法医学評論家としてテレビ・雑誌などで活躍している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
saga
36
戦前・戦中・戦後を生きた著者が、現代の日本を「自殺」という視点から書き上げた一冊。戦後教育しか知らない自分にとっては、考え方が少々古いと思うところもあるが、人を自殺に追い込んだ者が罰せられない歯痒さは感じる。法医学の知識・技能に優れた警察の検視官を増強する案は良いと思う。後半1/3を占める第4章は監察医務院での経験談が多く、著者の他の著作と共通する部分が多い。2017/04/21
ちさと
28
義務教育期間のこどものいじめによる「自殺」は、自我の確立がない以上自己責任とは言えず「他殺」と言えるのではないかというのが著者の主張。それは同じくいじめっこにも責任能力がないと言ってるのと同じかな。いじめは加害者が100%悪い。でも現代のいじめは教師も親も気がつかない陰湿なものが多いと聞くし、死を選ぼうとする人を見殺しにする=殺人は跳躍しすぎな気がしました。どんな死も、その死の原因を正しく究明して、生きている人間に還元したいという監察医としての著者の思いが詰まった一冊です。2018/12/05
鈴
18
自殺だと思ったら実は他殺だったという事案だけではなく、自殺の原因にはイジメなどがあり、それは他殺のようなものだというお話。著者のように遺体に真剣に向き合ってくれる監察医ばかりだと、亡くなった人も報われるんだろうに。2015/06/21
uD
16
元監察医である著者は「自殺は他人に追い詰められた末に行なうものなので、もはやほとんど他殺です」と主張します。 事故で人が亡くなったら、その原因をしっかりと追求し再発防止に努めるのが当たり前。しかし自殺の場合「尊い命が失われた」「悲しい出来事だった」と死の真相はうやむやに終わってしまうケースも少なくないのだそう。 年間3万人もの自殺者が出る日本の社会は、やはり何かがおかしいと思います。 「自殺は他殺のようなもの」 そう考えて、根本から改善していく姿勢は、ある意味必要に迫られてのことなのかもしれません。2018/10/14
たくのみ
13
二万人の遺体を検死してきた上野先生。「あと1日で保険がおりるから死亡日をずらして」「死因が自殺では世間体が…」「自殺や病死では会社が認めてくれない」検死官としての苦悩がつづられる。死亡推定時刻の割り出し、青、赤、黒、白と変化する腐敗の進行、リアルな検死の現場の描写が衝撃だった。自殺を生み出す社会へのやり切れない思いと、自殺の背景であるいじめ、過労、孤独、ストレスをなくしたいという思いがタイトルになったようだ。2014/06/04