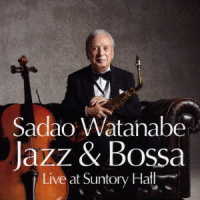出版社内容情報
日本は、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している。東シナ海では、中国の海軍艦艇の恒常的な活動の下、中国海警局に所属する船舶が尖閣諸島周辺の日本の領海への侵入を繰り返している状況にある。尖閣諸島の領海警備を担っているのは、海上保安庁である。海上保安庁は、海上保安庁法二五条により、国内法上、純粋な警察機関とされる。海上保安庁は、「海の警察・消防」と説明されることが多い。しかし、他国の艦船が目にするのは「COAST GUARD」という船体標記である。一般にコースト・ガードは、海上の国境警備を主な任務とする準軍隊を指す。この本来のコースト・ガードとの乖離が安全保障上の大きな争点となっているのである。本書では、中国の軍事的脅威が増す中、世界の主要国の中でも特異な海上保安庁法二五条に焦点を当てながら、海上における世界有数の実力組織である海上保安庁の役割を明らかにしていきたい。
目次
第1章 自衛隊による領域警備(能登半島沖不審船事案とグレーゾーン事態;不審船事案を受けた領域警備法制の議論;最近の領域警備法制の議論)
第2章 中国海警法が与えた影響(中国海警局の第二海軍化;自民党国防部会と国土交通部会の対立;自民党国防議員連盟の提言;日本維新の会の問題意識)
第3章 国家安全保障戦略等の改定(米国の国防費GDP比二パーセント以上の要求;日本国民の安全保障意識の高まり;自民党の提言と政府の有識者を交えた検討;新たな国家安全保障戦略の閣議決定)
第4章 軍警分離とパシフィズム(憲法九条と海上保安庁法二五条;「軍警分離」を唱えた飯田忠雄;国際法上の「軍警分離」の曖昧さ;ジュネーヴ諸条約上の問題;海上保安庁とパシフィズム)
第5章 海軍とコースト・ガードの連携(アメリカの国家艦隊計画;G7諸国の状況;東南アジア諸国の状況;日本の現状)
著者等紹介
亀田晃尚[カメダアキヒサ]
博士(公共政策学)。2020年、法政大学で博士号(公共政策学)を取得。法政大学大学院政策科学研究所特任研究員。日本政治法律学会、日本国際政治学会、日本政治学会日本法政学会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。