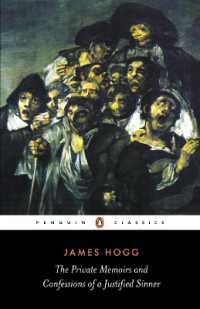- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 芸術・美術一般
- > 芸術・美術一般その他
内容説明
古代インドで万物創生の華として信仰された蓮。数千年にも及ぶ蓮に対する人々の想いは、見えない世界でうごめく根源の「いのちのかたち」を現世に顕現させた。インド・グプタ期に誕生したエネルギー形象・「グプタ式唐草」は、しなやかに変容をくりかえしながら東伝し、各地の美意識や信仰と交じりあっていく。まるで水が大地にしみこむように。仏教の「蓮華化生」の源流ともなった、永続するいのちのかたちの時空を超えた旅の軌跡。
目次
序論 唐草の神秘に魅せられて
第1章 ストゥーパの蓮華意匠―大蓮華から拡がるいのちの世界(バールフット欄楯浮彫装飾;サーンチー第二塔欄楯浮彫装飾;ボードガヤー聖地を囲む欄楯の蓮華意匠 ほか)
第2章 グプタ式唐草の世界―本源からのメタモルフォーシス(グプタ式唐草の登場;グプタ式唐草の顕現;エネルギーの核―此岸と彼岸の媒介者 ほか)
第3章 拡がるいのちのかたち―グプタ式唐草の東伝(絲綢之路;中国;朝鮮半島 ほか)
著者等紹介
安藤佳香[アンドウヨシカ]
美術史家。佛教大学教授。博士(文学)。徳島県文化財保護審議会委員、福井市文化財保護審議会委員、密教図像学会常任委員。『佛教荘厳の研究―グプタ式唐草の東伝―』(中央公論美術出版)で第15回國華賞受賞。大阪市出身(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Mentyu
3
瓦当文様に関する考古学的研究は山のように存在する。しかし、その文様が何を意味するのかという論点は基本無視されており、分類と編年に終始することが通例となっている。そんな瓦頭文様で、ド定番と言えるのが、本書の研究対象とした蓮華文と唐草文である。筆者によると、この2つの文様は、インド(仏教)世界における生命エネルギーの表現であり、それが日本へ東漸してきたという。瓦当文様の理解で一番重要なポイントであるはずの、その文様が何を意味するのかという問題は、結局、考古学ではなく、図像学的研究が明らかにしたのであった。2023/07/18