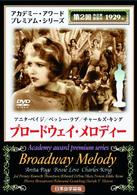内容説明
戦国時代、大名たちが苦心したのは有事の際の軍需物資の確保だった。なかでも木材、竹は重要で、築城はもとより、武器、武具、柵、旗指物、篝火、戦場での炊事用の薪といったように、戦略・戦術上必要不可欠なものだった。戦国大名は、領国内の木材を確保してはじめて合戦が可能となった。しかし、無制限に伐採をおこなうと森林資源は枯渇してしまうため、領国内の森林の管理は、戦国大名にとっては極めて重要だった。武器、武具や築城などに必要な森林資源を戦国大名たちがどのようにして確保、管理したのか?いままでにないまったく新しい側面から戦国合戦像を明らかにする。
目次
序章 合戦の勝敗は軍需物資の確保にあり!
第1章 軍用品の調達に奔走する大名たち
第2章 軍需物質を確保した大名が勝利をおさめた!
第3章 合戦・城攻めに使われた武器武具
第4章 武器・武具の調達方法を検証する
第5章 伐採と植林をくりかえした戦国時代
終章 戦国軍拡と自然環境の変化
著者等紹介
盛本昌広[モリモトマサヒロ]
1958年横浜市生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。東京都立大学大学院修士課程修了。専攻は日本中世・近世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ようはん
16
ある程度の規模の合戦をやるにしても柵はもとより槍や旗指物に大量の木や竹が使われ、篝火や松明、鉄砲や刀を作る鉄にしても大量の薪や炭が必要でいかに森林資源がどれ程重要だったかがよく分かる内容。当時からの乱伐で禿山は多かったが、戦国時代の時点で植林や資源保持の努力が行われておりまた割と森林が保たれていた寺社勢力周辺との資源を巡るやり取りも印象に残る。2020/09/25
May
4
(記録として昔の文章を)軍需物資=木材の利用、そしてその確保・生産が、戦国期においてどのように行われていたかをテーマとしたもの。また、利用はメインテーマでなく、そのための資源の確保・生産がメインテーマである (と思われる)ため、工夫の一環なのだろうが、「戦国期における木材資源の確保・生産について」という書名の方が、内容をより正しく伝えることができると思われる。また、木材にしろその他の物資にしろ、領主としてその確保に気を配るのは当然であって、これは洋の東西を問わない(西洋においても宮廷領なる領土があったし)2008/07/01
つゆ
2
野守、山守という存在がかつていた。政府より命を受け、無駄な・無許可な伐採が行われないよう監視する役割。戦国の世において木材や草は武器、燃料、家畜の餌など様々な用途で必要であり、軍を保つにはそれが大規模になればなるほど多量入手が不可欠であった。持続的供給を可能とするため、植物間の生態系の変化を防ぐため、という点において、不必要な伐採は監視され、同時に植林も行われていたが、そこに今日のように自然環境を保護・持続させるという視点があったかどうかは本著作より読み取ることはできず。2022/02/08
nakaji47
2
戦国の合戦に必要な竹木などの物資の調達、管理について、主に後北条氏の資料を基に分析した本。こうした自然科学的見地から戦国時代を論じたものは少なく、その意味は大きいと思う。度重なる戦乱により山林が荒れ、環境が大きく改変された可能性についての言及もあり、現代の環境問題にも通ずる点が歴史書として面白い。2010/05/09
にゃおまる
1
歴史物が奥深く読めるようになる。2019/03/31