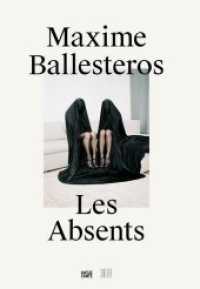内容説明
緊急の教育課題は「学力低下問題」か「子ども・若者問題」か?今日の教育不全は、学力低下にあるのではない。学ばない、学ぼうとしない子どもにこそあるのだ。なぜこれを直視しないのか?一九八〇年代中葉以後に顕著になった、子どもの変容を認めず、学校が悪い、教師がダメだ、といった犯人探しに右往左往し、挙句は、愛国心があればいじめがなくなるとか子どもは本来学びたがっているのだから、ダメ教師を査定して排除すれば子どもは学ぶはずだなどと現実を無視した、床屋政談にうつつをぬかす。わが子の成績だけにこだわる親と、競争と効率と市場の論理で教育を語るだけではこの国の教育再生はみえてこない。もうこの国はほんとうにだめなのか。
目次
1 「子どもが変わった」ことを認めない議論はすべて間違う
2 「ゆとり・生きる力」派の敗北と「学力向上」派の跳梁
3 「ゆとり教育」敗北後の小学校の実態を誰も知らない
4 陰山先生はそんなにえらいのか
5 「教育再生会議」はどこへ行こうとしているのか
6 市場の論理と教師査定で学校は活性化するか
7 イジメの正体とその解決法
8 「愛国心」は教育を再生するキーワードになり得ない
9 「できる子」と「できない子」はどのように差がついていくか
10 わが子だけ勝ち組になればいいのか?
11 教育を経済や政治のことばだけで考えてホントに大丈夫か
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
藤枝梅安
15
各章が独立しており、どこから読んでも一定の理解にたどり着くことができる。 現役の高校教諭である、喜入克(きいれ かつみ)さんの担当した「6:市場の論理と教師査定で学校は活性化するか」と 「7:イジメの正体とその解決法」は平易な言葉遣いで、事象を端的に表すキーワードを巧みに用い、問題点を非常に分かりやすく解きほぐしてくれる。この本は、行政側(政府・文科省)にも現場の「管理体制への反対勢力」のどちらにも偏らない立場で、冷静かつ合理的に問題に立ち向かおうとする筆者達の姿勢を紹介する性格となっている。2010/09/05
シン
11
勉強になった。2007/09/12
仲本テンカ
4
資本主義社会の末期。生徒自身がお客様になってしまった、授業風景。もはやソコには師弟の関係は無く、あるのは消費と生産の関係のみ。この現象は、多分、誰も悪くない。ただ、解決策なんて、もはやないって感じです。(自称)プロ教師の方々の戦々恐々ぶりが、たいへんよく伝わってきました。改善の兆しはありません。救いもあるようには思えません。とにかく、大混乱。先生たち、頑張ってね。2013/04/20
Don
0
読了。 かなり共感する部分があったので、後ほど。2013/08/15
kishikan
0
教師の側からの教育論と教育サービスを受ける側(実はそう思っているだけの)からの教育論の果てしなく続く論争を読み解くために参考となる。この本自体は教師側のメンバーによるものだが、比較的冷静な立場にあるので問題の焦点に辿りつき易い。ただし「プロ教師」という言葉は使ってほしくなかったなぁ。
-
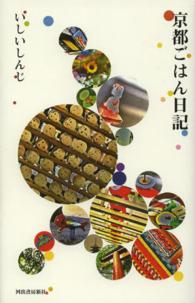
- 和書
- 京都ごはん日記