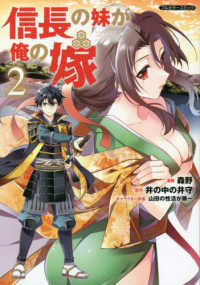内容説明
評判、歴史、実績、現実、選考、執念。本邦随一の研究家が徒然のままに綴った、トリビア満載の「直木賞」エッセイ。直木賞受賞作一覧・付。
目次
1 直木賞は、ほんとにすごいのか。すごくないのか。
2 八十ン年、よくめげずに続けてきました。
3 受賞がもたらす、ささやかな出来事。
4 とらなかった作品のほうこそ、直木賞って面白い。
5 文学性+エンタメ性、という難問にみんな大わらわ。
6 直木賞はなくてもいい。けど、あったっていい、ですよね?
著者等紹介
川口則弘[カワグチノリヒロ]
1972年東京都生まれ。直木賞研究家。筑波大学比較文化学類卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
修一朗
63
川口則弘サンの人気サイト「直木賞のすべて」にはお世話になっている。毎度,直木賞発表のたびにアップされる講評を楽しみにしているのに加え,昔の落とされた候補作を眺めては「ええっ,これってこの作品に負けはったの?信じらんない」なんて感慨にふけるのも楽しいのだ。「芥川賞の偏差値」だとか「このミステリーがひどい」なんて変な本を書く小谷野敦さんとお友達だったのには驚いた。平成以降の直木賞受賞作をコンプリートすることが目標の一つだけど,年食ってばかりでさっぱり進まないので結構高いハードルになってしまったなぁ… 2017/03/12
そうたそ
36
★★★☆☆ 前作「直木賞物語」が直木賞入門編的なテキストであったとすれば、本作は直木賞について割とディープなところにまで踏み込んだ上級者向けの一冊であるといえるかもしれない。とはいっても、決して読者を置き去りにして薀蓄披露に暴走しているわけではないので、直木賞をあまり知らないという人が読んでも十分楽しめる内容になっている。とにかく驚いたのは、さすが直木賞オタクだというだけあって、こんなにも直木賞に関する裏話があったのかと驚いてしまうほど、多数のエピソードが盛り込まれている。読んでみたくなった作品も数々。2016/03/31
ばりぼー
31
1969年~78年の直木賞は、「苦悩の時代」である。該当作なしが9回と、その役目を果たしていない。いまの直木賞は、「エンタメ小説全体のクオリティを示すバロメーター」では全然ないが、70年代ぐらいまでは、そうありたいという「志」を賞の奥底に漂わせていた。しかし、苦悩の時代をくぐり抜けた末に、直木賞はその志を脱ぎ捨て、あえて時代についていくことをやめた。その大きな分岐点になったのが、山田正紀『火神を盗め』の登場と落選である。直木賞は「おもしろい小説」に背を向け、そのテリトリーを狭める方向へと舵を切っていった。2020/03/15
洋
24
直木賞受賞作は可能な限り読んでいきたいって思っています。受賞に値する作品かとか文学的にどうか なんて事はあたしには分かるはずはなくて、ただ読書の幅が広がればいいなぁ…と。残念ながら受賞を逃してしまった作品の中にも良作がたくさんある事だったり選考委員のあれやこれや、直木賞の裏側が満載でした。2016.02.182016/04/03
ぐうぐう
22
『直木賞物語』の川口則弘、そのオタクっぷりがわかる最新刊。ブログのエッセイを再構成したものなので、嘲笑的な文体には正直馴染めないが、ブログゆえの遠慮のなさは心地いい。世間や文壇にはびこる直木賞のイメージを「本当はそうじゃないんだよね」と実例を挙げ修正していきながらも、その誤解こそが直木賞なのだと居直り、楽しもうとするのが川口の基本的な姿勢だ。『直木賞物語』を読んだときにも感じたことだが、人が書いたものを複数の人が選ぼうとするわけだから、結局のところ、直木賞とは生き物なのだ。だからおもしろい。(つづく)2016/05/04