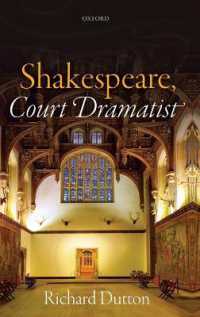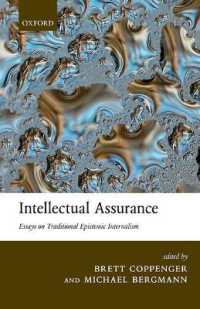内容説明
夜の闇にひっそりと佇む夜間定時制高校。そこには、時代の矛盾が見事なほどに堆積していた!ヤンキー系、いじめ被害者、元・援交少女、被虐待児、リストカッター、性犯罪被害者…さまざまなアウトサイダーが集う、教育システム最底辺校で見たリアルな日本の現実。生きることに希望を見い出せない貧しい人々の世代間連鎖。親と子、地域社会、あらゆる関係が分断される孤独大国・日本。格差、ワーキングプア、闇社会、精神の病…時代の矛盾を真っ先に受け止める若者たちに、いま何が起こっているのか?その最前線を伝える衝撃のノンフィクション。
目次
序 炭坑のカナリアたち
1 居場所としての夜間定時制高校
2 自分を傷つける若者たち
3 家庭が壊れている
4 暴力という生き方
5 商品化される「性」を生きる少女たち
6 マイノリティたちの夜間定時制
7 夜間定時制という番外地はいま
著者等紹介
瀬川正仁[セガワマサヒト]
東京生まれ。映像ジャーナリスト。1978年、早稲田大学第一文学部卒業。80年代後半より映像作家としてアジア文化、マイノリティ、教育問題などを中心に、ドキュメンタリーや報道番組を手がける。日本映画監督協会会員。日活芸術学院講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
katoyann
13
東京都にある夜間定時制高校を取材したルポ。複雑な背景のある生徒が集まる高校のリアルを描いている。学校で傷つけられた経験を持つ子どもが多いこともあって、不思議と他人の失敗を嘲笑うような文化は生まれず、いじめが深刻化することもないという。もちろん、やんちゃな子が多く、校内での喫煙は当たり前であるが、定時制高校の先生はそれを直ちに咎めることなく、見守っているのだという。具体的な非行歴のエピソードを読むと大変そうだが、一貫して学力至上主義の矛盾を批判する著者の姿勢が素晴らしいと思った。2025/08/29
タケシ
2
夜間定時制高校に通う若者たちを取材したノンフィクション、かと思って読み始めたら、とんでもないインチキ本でした。 この本によると、定時制高校に通うのは「障害者」「精神病患者」「家庭内暴力を受けてきた人」「ヤクザの手下」「レイプ被害者」等々。 よくもまあこれだけ特殊な例を、さも「定時制高校に通うのはこんな人ばかりです」と涼しい顔で書けるもんです。 定時制高校卒業生として許し難い本でした。 そりゃこれだけ特殊な例をズラズラ書けば、面白おかしくもなりますよ。 取材力と文章力の無さがありありと解る、最低な本でした。2017/09/12
彩灯尋
2
どんな形であれ、学びたいと思っている若者を受け入れる姿勢は大切。少し道が外れてしまっても、決してそれは終わりではなく、自分が変わりたいと思えばいくらでも修復は可能だと思う。その手助けとなることは社会が受け入れるという体制を作ること。問題行動があったから学校を追い出すのではなく、その人にあった形を探すべき。このルポが書かれたのは2009年だが、現在教育機関の多様化の現状はどうなっているのだろうか。2015/08/11
katta
2
前作『老いて男はアジアを目指す』が面白かったので、新作も読んでみた。夜間定時制高校に通う様々な事情を持った生徒達に取材し、この学校の必要性を説く。ある意味、日本の最下層に位置されてしまった若者たちと、かつての若者の再生を目指す物語は、少しの希望と多くの落胆で形作られていく。2009/07/06
Jagrass03
1
自分も定時制だったので懐古に浸りつつ読んだ。どこも同じなんだなという感慨を抱き、学校スポーツに対して唱える問題点に共感した。子持ちで学校に来る生徒もいたなーなどと懐かしくなると同時に、定時制の山積した問題の解決の難しさを想像すると暗澹たる気持ちになった。2010/04/13