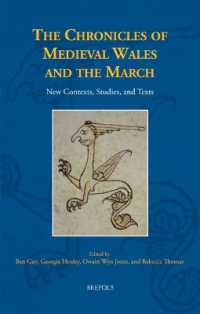内容説明
井戸茶碗は雑器?それとも神のための器?秀吉や利休を魅了した井戸茶碗は、時を経て日本の国宝となっている。しかし、井戸茶碗には「謎」が多い。いまだ窯すら限定できず、韓国では同種のものさえ発見されない。韓国の陶工が日韓を往復し、探し求めた「井戸茶碗の正体」。実作者でなければ語ることのできない、歴史ミステリーにして、もうひとつの日韓文化史。
目次
1 井戸茶碗とはなにか
2 井戸茶碗は祭器だ
3 韓国陶磁器の歴史
4 高麗茶碗の故郷を訪ねて
5 土と釉薬
6 陶工の火の物語
著者等紹介
申翰均[シンハンギュン]
陶工。韓国の高麗茶碗を最初に再現した陶芸家・申正煕(シンジョンヒ)の長男として、1960年、慶尚南道の泗川で生まれた。毎年画廊にて招待展を開いており、1993年に韓国工芸大典で銅賞を受賞。1996年に国内で初めて会寧釉薬を再現した。現在は慶尚南道の梁山市にある韓国三宝寺刹のひとつである「通度寺」の近くで作陶活動をしながら、韓国陶磁器の本質を究めるために、韓国・日本間を往来しながら活動中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
じぇいじぇい
2
韓国の陶芸家・申翰均(シンハンギュン)が、日本で国宝に指定されることもある「井戸茶碗」について書いた本だ。多くの人が、井戸茶碗とは最初は「雑器」、つまり「貧乏人が普段ざらに使う茶碗(柳宗悦)」だった、と考える。だが筆者は、先祖に食事を供えるための「祭器」だった、と考える。ビワ色は真鍮を模倣し、ろくろの跡はもっと古い祭器の模様を簡略化したものであると言う。高い高台は匙でご飯を食べる韓国では実用的ではなく、これも祭器の証拠だという。2章まで以上の井戸茶碗についての考察で、3章からは韓国の簡単な陶器史などだ。2011/06/07
-
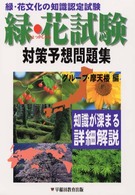
- 和書
- 緑花試験対策予想問題集