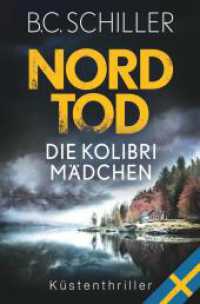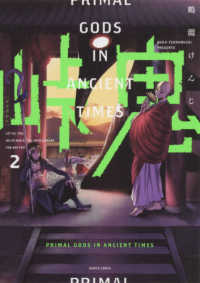目次
第1章 理性の構築―『狂気の歴史』(「理性の不安」;狂気と理性:『狂気の歴史』;デカルトの懐疑;「大いなる閉じ込め」;中世における「狂気」;近世以降;狂気経験の構造)
第2章 知の台座―ヨーロッパ的知という構造(思考の土台:エピステーメ;動植物についての知;エピステーメが生み出すもの)
第3章 パノプティコン―自己規制によって作られる自我(死の権力;生の権力;規律)
第4章 「私空間」の編成―『性の歴史1』
第5章 生政治と自己への配慮―抵抗の拠点?
著者等紹介
貫成人[ヌキシゲト]
現在、専修大学文学部教授。1956年、神奈川県に生まれる。1985年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。現象学をはじめとする現代哲学、歴史理論、舞踊美学を研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りん
16
哲学というと抽象的な概念の話でわかりにくいというイメージだ。しかしフーコー自体が以前の哲学とは違うアプローチをしていることもあるだろうがそれを差し引いてもとても分かりやすく書かれている本だと思う。自分たちが真理に基づいて制度化され権力に規制されるがその前提は虚構であるという概念は不気味で救いがないがその構造を俯瞰する視点を獲得することで、世界の見え方や考え方は変わるし、そういう所が哲学の面白い所だと思う。しかしその獲得した構造さえもフーコーの言うエピステーメの変化によって否定され得るかもしれないとか考えだ2015/12/31
ふみすむ
16
ポストモダンの思想というと、いかにも難解そうで、本当に中身(実体)があるのか疑わしいというイメージがつきまとう。ただ、本書を読んだ限り、フーコーに対しては、多くの人が近代以後の社会の中で薄々気づいている(身近な)断片をまとめ上げたうえでその文章化に成功した思想家、という印象を抱いた。フーコーは『狂気の歴史』『言葉と物』では人間の理性を問い、『監獄の誕生』『性の歴史Ⅰ』では近代的主体を問題にしている。いずれも近代においては自明とされた概念である。2015/06/25
beside image
8
フーコーについての入門書ということで読んでみたが、コンパクトな割に内容の濃いものとなっている。この本を一読すると、いかにあまたの「入門書」が「入門書でなかった」かを、つくづく思い知らされる。ここでは、余計なバイオグラフィーや、よくある著者のくどくどとした熱い思いは必要とされない。とにかく無駄がなく、スッキリとまとめられているのが素晴らしい。フーコーの哲学の紹介のみにとどまらず、デカルトやカントを挙げながら、著作の解説に沿いつつも、絶妙なバランスで実際にフーコーの哲学を演じてみせている。2013/12/03
佐藤一臣
7
一般施療院による大いなる閉じ込めは怖いね。十羽一からげで非理性を隔離するのはのちの政治的全体主義を予感させる。17~18世紀の表面分類と19世紀の内部機能分類という知的枠組みであるエピステーメーはわかりやすかった。著者は自分の言葉で平易に解説しようとしてくれているので、読んでいてストレスなく理解はできた。けれども、フーコーの悩みや彼がもろもろの思想に至る過程が詳細には描かれていないので、これでフーコーがわかったとは言えない気がする。課題図書としては良いかもしれない2025/08/16
ポカホンタス
6
『歴史の哲学』を読んで以来、貫先生のファンになった。たまたま本屋でみつけたこの本は、大変わかりやすくかつ深いレベルでフーコーの思想を解説してくれていて、さらにファンになった。帯に「ダンスを愛する著者らしく、語り口もリズミカル」と鷲田清一の文がある。確かにその通り。哲学の本なのに、語り口がいい。いくらわかりやすく解説されていても語り口が悪いと消化できない。本書は、身体レベルで哲学を理解することを実践している気がする。このシリーズ、全19巻すべて貫先生が執筆予定。既刊のものはまだ4冊。全部読みたい!2017/12/24