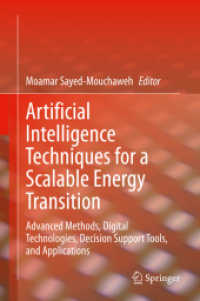出版社内容情報
本書では史料と現地調査、考古学の成果によりながら、さして俎上にものぼらなかった鎌倉街道の中道と下道の実態解明に挑む中世の鎌倉街道には、上・中・下の主要な3ルートがあるのは確かだが、その規模や形状、どこをどう走っていたのか、支線はどうなっているのかなど、実はわからないことのほうが多い。本書では史料と現地調査、考古学の成果によりながら、さして俎上にものぼらなかった中道(なかつみち)・下道(しもつみち)の実態解明に挑む。
序論 中世大道の成立と鎌倉街道……………………高橋 修(茨城大学教授)
第1部 論考編
金砂合戦と鎌倉街道……………………………………木村茂光(東京学芸大学名誉教授)
鎌倉街道と町場…………………………………………宇留野主税(桜川市教育委員会)
小田城と常陸の中世道…………………………………越田真太郎(桜川市教育委員会)
下野の鎌倉街道…………………………………………江田郁夫(栃木県立博物館)
下総西部の鎌倉街道中道………………………………内山俊身(茨城大学非常勤講師)
中世下総国毛呂郷域の「鎌倉大道」…………………清水 亮(埼玉大学教授)
考古資料からみた茨城県内の中世道路………………比毛君男
第2部 資料編 鎌倉街道下道現況調査報告
資料編凡例
下総との国境湿地に浮かぶ台地の道…………………前川辰徳(大田原市那須与一伝承館)
内海世界と下道を結ぶ…………………………………額賀大輔(笠間市教育委員会)
霞ヶ浦を望む桜川・花室川の渡河点…………………比毛君男(土浦市上高津貝塚ふるさと歴史の広場学芸員)
常陸国府と筑波に通じる二本の道……………………千葉隆司(かすみがうら市歴史博物館)
五万堀古道………………………………………………大関 武(つくば市立要小学校教頭)
筑波山南麓の東西道……………………………………越田真太郎
下野国と奥大道をつなぐ小栗への道…………………宇留野主税
高橋修[タカハシオサム]
高橋 修(たかはし おさむ)
1964年生れ、茨城大学人文社会科学部教授
〔主な著書〕
『中世武士団と地域社会』(清文堂出版)
『熊谷直実?中世武士の生き方?』(吉川弘文館)
『常陸平氏』(編著・戎光祥出版)
『信仰の中世武士団?湯浅一族と明恵?』(清文堂出版)
『佐竹一族の中世』(編著・高志書院)
宇留野主税[ウルノチカラ]
宇留野 主税(うるの ちから)
1973年生れ、桜川市教育委員会生涯学習課副主査
〔主な論文〕
「戦国期真壁城と城下町の景観」(『茨城県史研究』第92号)
「中世城館の成立過程」(『アーキオ・クレイオ』第10号、東京学芸大学)
「堀・堀内障壁〔障子堀〕」(『中世城館の考古学』高志書院)
目次
序論 中世大道の成立と鎌倉街道―常陸・北下総の事例から
第1部 論考編(金砂合戦と鎌倉街道;鎌倉街道と町場―常陸国中郡の宿と町;小田城と常陸の中世道;下野の鎌倉街道―中世会津街道を中心に;下総西部の鎌倉街道中道;中世下総国毛呂郷域の「鎌倉大道」;考古資料からみた茨木県内の中世道路)
第2部 資料編―鎌倉街道下道現況調査報告(下総との国境湿地に浮かぶ台地の道―北相馬郡利根町;内海世界と下道を結ぶ―牛久市岡見とその周辺;霞ヶ浦を望む桜川・花室川の渡河点―土浦市;常陸国府と筑波に通じる二本の道―かすみがうら市;五万堀古道―笠間市;筑波山南麓の東西道―土浦市;下野国と奥大道をつなぐ小栗への道―桜川市・筑西市)
著者等紹介
高橋修[タカハシオサム]
1964年生れ、茨城大学人文社会科学部教授。主な著書に『信仰の中世武士団‐湯浅一族と明恵‐』(清文堂出版)、『佐竹一族の中世』(編著・高志書院)など
宇留野主税[ウルノチカラ]
1973年生れ、桜川市教育委員会生涯学習課副主査。主な論文に「中世城館の成立過程」(『アーキオ・クレイオ』第10号、東京学芸大学)、「堀・堀内障壁〔障子堀〕」(『中世城館の考古学』高志書院)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。