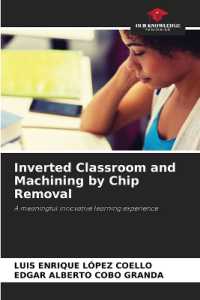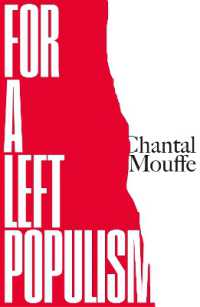出版社内容情報
TPPにも負けない「強い農業」とは地産地消と有機農業だ。身近な資源を活かし、自給をベースにした循環型の地域づくりが明日を拓く
TPPを乗り越える「強い農業」とは、地産地消と有機農業
地域資源を活かした中山間地の豊かな取組み=地域自給が明日を拓く
序 章 改めて地域自給を考える 桝潟俊子
1 農山村における生存・生活基盤の危機
2 地域自給の現代的意義
3 原発被災地での農の営み
4 土と自然、人につながり、ネットワークのもとで生きる
第?T部 中山間地の地域自給の実践と成果
第1章 木次乳業を拠点とする流域自給圏の形成 井口隆史
1 生き字引・佐藤忠吉
2 小規模酪農複合経営の形成と有機農業への試行錯誤
――第一期(一九五三~七一年)
3 木次有機農業研究会の結成と風土に根ざした地域自給思想の確立
――第二期(一九七二~八一年)
4 産消提携運動の拡大・深化とモノカルチャー化への対応
――第三期(一九八二~九六年)
5 有機農業と流域自給・自立のシンボルとしての「食の杜」づくり
――第四期(一九九七~二〇一二年)
6 流域自給圏安定に向けての課題と新しい可能性
第2章 地域資源を活かした山村農業 相川陽一
1 山村に根ざした農のあり方
2 小規模・分散・自給・兼業の価値を見直す
3 弥栄の概要
4 有機農業の展開
5 山村自給農の継承に向けて
6 山村の自給農は持続可能な社会のモデル
第3章 資源循環型の地域づくり
内容説明
地域資源を活かした農山村の取り組み、歴史と風土に根ざした自給農や地産地消、有機農業をめざす自治体政策…持続可能な自立した社会を創る。
目次
改めて地域自給を考える
第1部 中山間地の地域自給の実践と成果(木次乳業を拠点とする流域自給圏の形成;地域資源を活かした山村農業;資源循環型の地域づくり)
第2部 自治体と有機農業(自給をベースとした有機農業―島根県吉賀町;島根県の有機農業推進施策)
第3部 地域に広がる生産者と消費者の新たな関係(生産者と消費者による学習・交流組織の形成と展開―しまね合鴨水稲会;大学開放事業から生まれた生産者と消費者の連携)
これからの地域自給のあり方
資料 自給的農業としての有機農業―日本有機農業学会2011年度公開フォーラムin雲南
著者等紹介
井口隆史[イグチタカシ]
1943年生まれ。島根大学名誉教授、「たべもの」の会代表
桝潟俊子[マスガタトシコ]
1947年生まれ。淑徳大学コミュニティ政策学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
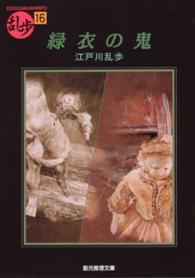
- 和書
- 緑衣の鬼 創元推理文庫