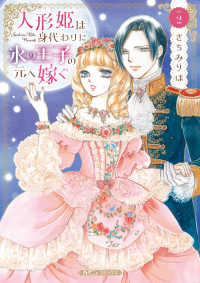出版社内容情報
東京の片隅に肩を寄せ合って暮らす夫婦のしみじみとした愛情を描いた小説『門』
自らと読者が生きている社会・生活・世相を活写した作家・漱石。ハルビンでの伊藤博文暗殺に始まる『門』から、激変する明治末のさまざまな世相(家計、電車、盛り場、メディア、探偵、アジア進出、社会主義……)を読み解く。
夏目漱石の『門』は地味な小説だ。/ふたりの男女が所帯をもって、東京の片隅に移り住んで、肩を寄せ合って生活している、というただそれだけの物語だ。/『坊つちやん』『三四郎』『こゝろ』が私たちの青春時代の漱石体験だとすれば、『門』を読んだ人は、おそらく青春がすぎて、漱石とふたたび出会った人ではないだろうか。……『門』が「朝日新聞(東京・大阪)」に連載されたのは、一九一〇年(明治四三)三月一日から六月一二日だが、小説内の時間は、その前年の〇九年一〇月末から始まっている。……漱石のほとんどの新聞小説は、描かれた時代が掲載時のほぼ半年前から前年という同時代性が大きな特徴だ。そのことが、小説を丁寧に読めば、そこからその時代の世相を読みとることができる、という性格をもっているのだ。(本書「はじめに――『門』を読んで考えた」より)
内容説明
東京の片隅に肩を寄せ合って暮らす夫婦のしみじみとした愛情を描いた小説『門』。自らと読者が生きている社会・生活・世相を活写した作家・漱石。ハルビンでの伊藤博文暗殺に始まる『門』から、激変する明治末のさまざまな世相(家計、電車、盛り場、メディア、探偵、アジア進出、社会主義…)を読み解く。
目次
第1部 東京の暮らし(家計―国家公務員でも弟の大学の学費を払えない!;電灯と電車―山の手の奥から電車で丸の内に通勤;盛り場・神田―銀座の前の盛り場は神田だった)
第2部 メディアと暴動(内務省の「官僚」と足尾の「坑夫」―東京帝大出のエリート官僚の全国統治;伊藤博文と新聞―醜聞報道をエサにする権力者;泥棒、探偵、高等遊民―「探偵」が漱石のキイワードになったわけ)
第3部 アジアへ(満州、朝鮮、蒙古意識を探る―借家住まいにも、満州・朝鮮・蒙古の話題が)
第4部 近代と病(社会と世間―近代と前近代の規範が錯綜する;病い―胃腸を病んでいたが、糖尿病で急逝)
著者等紹介
中西昭雄[ナカニシテルオ]
1941年東京生まれ。京都大学文学部卒。65年、朝日新聞社に入社し、「アサヒグラフ」「週刊朝日」「アサヒカメラ」などに勤務。81年退社。月刊誌「ペンギン・クエスチョン」(現代企画室)を編集。85年、編集工房「寒灯舎」を設立。「日本寄せ場学会」(87年)、「日本の戦後責任をハッキリさせる会」(91年)創設に参加(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
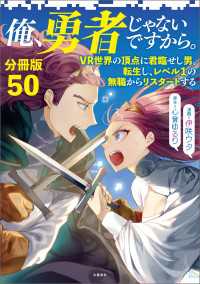
- 電子書籍
- 【分冊版】俺、勇者じゃないですから。(…
-
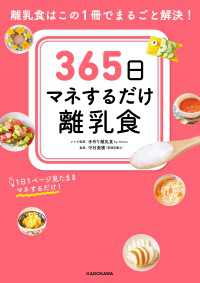
- 電子書籍
- 365日マネするだけ離乳食 離乳食はこ…
-

- 電子書籍
- お化けカフェ 1 NETCOMICS
-

- 電子書籍
- りとる・ラブ 〈3〉 魔法のiらんど文庫