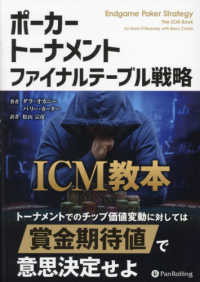出版社内容情報
内戦で萌芽し、独ソ戦を勝利に導き、冷戦時、アメリカと伍した、最強のソフト。現代用兵思想の要、「作戦術」とは何か? ソ連の軍事思想研究、独ソ戦研究の第一人者が解説する名著、待望の初訳。
作戦術(Operational Art)とは?
ソ連は、第二次世界大戦前に、画期的な用兵概念である「作戦術(Operational Art)」を世界で初めて明確に定義し言語化することに成功。この作戦術は、独ソ戦においてソ連軍の勝利に貢献した。そしてアメリカ陸軍も、ベトナム戦争での敗北を機に、この「作戦術」の概念を自軍の軍事ドクトリンに導入。湾岸戦争で勝利を収める大きな原動力となった。
現在、世界の主要国の軍隊では、この「作戦術」という用兵概念はすでに常識となっている。
内容説明
内戦で萌芽し、独ソ戦を勝利に導き、冷戦時、アメリカと伍した、最強のソフト。現代用兵思想の要、「作戦術」とは何か?ソ連の軍事思想研究、独ソ戦研究の第一人者が解説する名著の初訳。原書全図収録・ソ連軍主要兵器の解説付。
目次
第1章 ソ連の戦争研究
第2章 作戦術の特質
第3章 作戦の枠組み
第4章 ソ連作戦術の形成期―一九一七~一九四一年
第5章 大祖国戦争と作戦術の成熟―一九四一~一九四五年
第6章 作戦術と軍事における革命
第7章 軍事における革命の改善
第8章 将来に関する見通し
著者等紹介
グランツ,デイヴィッド・M.[グランツ,デイヴィッドM.] [Glantz,Colonel David M.]
ヴァージニア軍事研究所およびノースカロライナ大学卒。ベトナム戦争に従軍。1993年、米陸軍を退役。最終階級は大佐。数多くのアメリカの軍事史雑誌の編集に携わるかたわら、米陸軍の各種学校で軍事史研究の講座を担当。著書には、第2次大戦の、特に独ソ戦に関するものが多数ある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
にしの
てっき
八八
マンシュタイン
jntdsn13