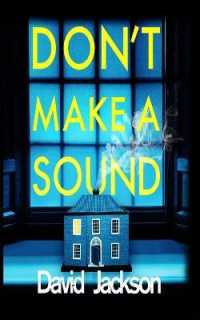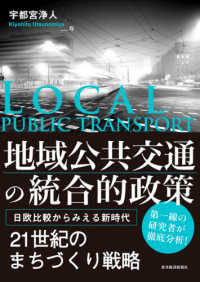- ホーム
- > 和書
- > 文芸
- > 海外文学
- > その他ヨーロッパ文学
著者等紹介
ハーセ,ヘラ・S.[ハーセ,ヘラS.] [Haasse,Hella S.]
1918年2月2日、旧オランダ領東インド・バタヴィア(現インドネシア共和国ジャカルタ)生まれ。父親の仕事の関係で20歳までを同地で過ごす。1938年、大学進学のため単身オランダへ渡り、アムステルダムで生活を開始。翌年第二次世界大戦が勃発、1940年5月からはナチスドイツ占領下となった同地で暮らしつつ、演劇を学び、さまざまな文芸活動を始めた。戦後1948年のオランダ全国読書週間の際に刊行された『ウールフ、黒い湖』が大反響を呼び、新進作家ハーセの名はオランダ国内に一気に知れ渡った。その後60余年に及ぶ長い作家生活の中で、劇作、詩作も含め、長篇歴史小説、少女時代を過ごした東インドを題材とした小説や現代小説、自伝的エッセイ、文芸評論を多数執筆、戦後オランダ文学を代表する文豪となった。2011年9月29日、アムステルダムの自宅にて永眠。享年93
國森由美子[クニモリユミコ]
東京生まれ。桐朋学園大学音楽学部を卒業後、オランダ政府奨学生として渡蘭、王立ハーグ音楽院およびベルギー王立ブリュッセル音楽院にて学び、演奏家ディプロマを取得して卒業。以後、長年に渡りライデンに在住し、音楽活動、日本のメディア向けの記事執筆、オランダ語翻訳・通訳、日本文化関連のレクチャー、ワークショップなどを行っている。ライデン日本博物館シーボルトハウス公認ガイド(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
Willie the Wildcat
エル・トポ
Christena
Wisteria
-
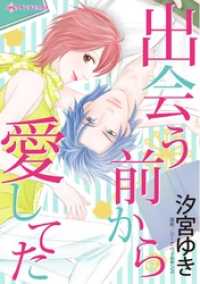
- 電子書籍
- 出会う前から愛してた【分冊】 3巻 ハ…
-

- 和書
- 上海キャンディ