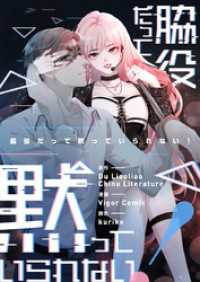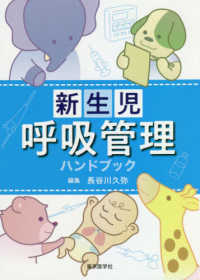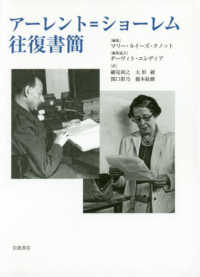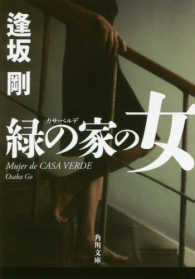出版社内容情報
押井守[オシイマモル]
笠井潔[カサイキヨシ]
内容説明
あの時代、同じ空気を吸っていたクリエーター二人が、当事者として語る貴重な時代の証言と“創造”の原風景、そしてそこから逆照射される“今”。あれから、半世紀をへた、この国とTOKYOの姿を、徹底的に語り尽くす。
目次
第1部 ルーツ―68年世代の僕らをつくったもの(今、68年を語る―もしかしたら、僕らは、「粛清」されたかもしれない;両親―前世代への反動、受け継いだ記憶)
第2部 リアルと表現をめぐる対話(衝動―表現に駆られる痛切な動機;身体性をめぐって―「危険の感覚を忘れてはならない」;「神」、「天使」、「吸血鬼」―「主体化できない、超越的なものを持てない」ものの意匠について;作家と作品―最終戦争からゼロ年代総括まで)
第3部 ルーツと生きること、創造すること(日本という国の正体―戦後民主主義・システム・物語;「境界線」上を生きる―この国で、創造していくこと;単独者と例外者)
著者等紹介
笠井潔[カサイキヨシ]
小説家・批評家。1948年、東京都生まれ。『バイバイ、エンジェル』で作家デビュー。1990年代以降は、本格ミステリの興隆にかかわる。2003年、『オイディプス症候群』(2002年)、『探偵小説序論』(2002年)で、本格ミステリ大賞の小説部門と評論・研究部門をダブル受賞
押井守[オシイマモル]
映画監督・演出家。1951年、東京都生まれ。タツノコプロダクションに入社、TVアニメ『一発貫太くん』で演出家デビュー。その後、スタジオぴえろに移籍、のちにフリーとなり『機動警察パトレイバー』シリーズ(1988~1993年)などを手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ムッネニーク
ぐうぐう
kei-zu
ndj.
ポン・ザ・フラグメント