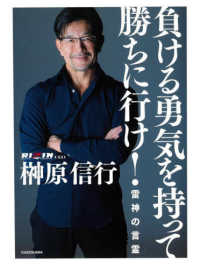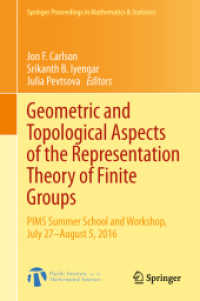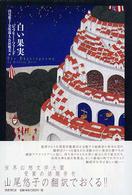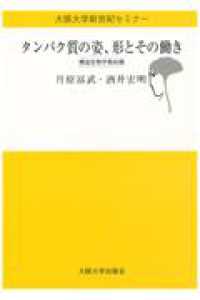内容説明
パース/ジェイムズ/デューイから、記号論/分析哲学/ネオ・プラグマティズムまで。ポストモダン以降、どう“使える”思想なのか?「アメリカ人特有の実用的で使える」という浅薄な理解を退け、原書を徹底的に読み解きながら、その壮大な世界観とはたして何に「使えるのか?」の核心を、現代思想の第一人者が、本格的に教える。
目次
第1回 プラグマティズムの本質―イントロダクション+ジェイムズ『プラグマティズム』を読む1
第2回 プラグマティズムが目指すもの―ジェイムズ『プラグマティズム』を読む2
第3回 「真理」について真剣に考える―ジェイムズ『プラグマティズム』を読む3
第4回 哲学観の変化―デューイ『哲学の改造』を読む1
第5回 哲学本来の役割とは?―デューイ『哲学の改造』を読む2
第6回 未来の思想?―デューイ『哲学の改造』を読む3+ネオ・プラグマティズムとは?
著者等紹介
仲正昌樹[ナカマサマサキ]
1963年広島生まれ。東京大学総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程修了(学術博士)。現在、金沢大学法学類教授。専門は、法哲学、政治思想史、ドイツ文学。古典を最も分かりやすく読み解くことで定評がある。また、近年は、ベンヤミンを題材とした『純粋言語を巡る物語―バベルの塔1』(あごうさとし作・演出)などで、ドラマトゥルクを担当。演劇などを通じて精力的に思想を紹介している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
呼戯人
16
ジェームズの「プラグマティズム」とデューイの「哲学の改造」を主に取り上げ詳しく読解してゆく形式の講義録。デリダ亡きあと哲学のフロントが消え去ったかに見える現状でプラグマティズムは数少ない希望の灯火の一つである。民主主義と立憲主義が侵される現状にあって、これを守り育てる智恵の一つとしてプラグマティズムは聳え立っている。それは連帯と自由の哲学であり、私たちの集団的生を支える原理を根本から考えている。それは、カントやヘーゲルの影響を受けているが、それを超え出てゆこうとする哲学である。2016/04/12
呼戯人
14
デューイの哲学改造の注釈を読んでいて、思い出したことがある。私は、幼いころから想像の世界、想念の世界に遊ぶことが多く、その世界を構築し、その世界に生きることが人生の意味だと考える習性があった。それゆえ、物質的世界、慣習の世界、生理的必要を満たす行為をなるべく最低限に抑えようという衝動が強かった。そのため現実的な世界と衝突することが多く、なかなか生理的な人生の必要を満たす行為に満足を覚えることがなかった。これが本末転倒の苦しみであることに気付いたのはつい最近のことである。これが観念論の根にある衝動である。2017/05/03
さえきかずひこ
10
第4回〜5回のデューイ『哲学の改造』の解説がとても面白かった。この2章を一読するだけで、プラグマティズムというと、何か非哲学的なものの考え方をするのではないかという初学者の思い込みが完全に粉砕されると思う。デューイが西洋哲学の生み出した二項対立図式を歴史的に概観し、批判していく過程がよく理解できたし、その点でもプラグマティズムは哲学だということがよく分かった。著者による誤訳の細かな訂正や、レベルの高い質疑応答の数々もたいへん勉強になる。じゅうぶんに理解したとは思えないので機会があればまた再読したい。2018/04/01
中年サラリーマン
10
合理論でもなく経験主義でもなく、それらを超える意味でのプラグマティズム。先端実験科学の影響を受けた現代的な思想だと思う。ただ、科学実験は不完全帰納法だからこれまでの理論の反例が出れば棄却されるため、終着点はないけど、それにこだわらずむしろプロセスにこだわるのがプラグマティズムかもね。2016/11/25
またの名
8
「素朴な実践思想とプラグマティズムは相性がいいと思ってる人もいるかもしれないけど、そんな単純ではないし、本気で「理屈などいらない!」と思っている人は、プラグマティズムの注釈本さえ読まないでしょう」という(笑)を付けた方が良さそうな恒例の仲正節。何かが真理かどうかより実際に使えることを重視する哲学運動について回る軽薄ではとの疑いを、原典の語学的検討や明記されていない文脈への言及によって晴らしていく明快な講義。自分は大理論を展開するタマじゃないと謙遜しつつも仲正無双で爆進中の解説講義シリーズに、さらに期待。2019/03/31