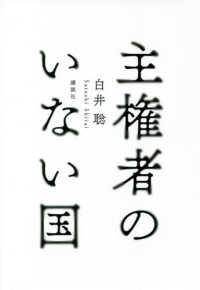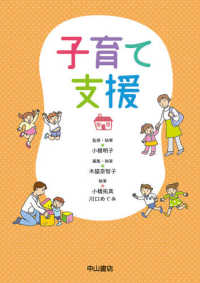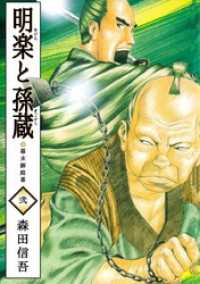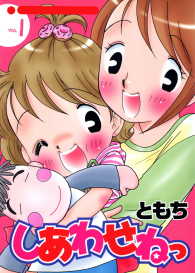内容説明
世界の文学の現場から日本にどう向き合うのか、日本にいながら境界を越えていかに世界へ。20年にわたる文芸時評を通じて、文学の“現在”を照らし出す、著者初の文芸時評集。
目次
1993‐1994 『海燕』文芸時評
1995‐1997 『読売新聞』文芸季評
1998‐2001 書評&エッセイ
2002‐2003 『朝日新聞』文芸21
2004 書評&エッセイ
2004・12‐2011・12 『新聞三社連合』文芸時評
著者等紹介
沼野充義[ヌマノミツヨシ]
1954年東京生まれ。東京大学教授。ロシア・東欧文学専攻。著書に『亡命文学論 徹夜の塊』(サントリー学芸賞)『ユートピア文学論 徹夜の塊』(読売文学賞、ともに作品社)ほか(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キョウラン
11
1993年から2011年の文学の流れがわかる本。あーこの年に綿矢りさや金原ひとみがブレイクしたなあとか。文学は衰退したとか死んだとか言われてもいやまだまだ文学ですべてを表現してはいないはず……?いやまだ書かれていないなにかがあるのかもしれないし無いかもしれない。でもまだまだこれから混迷の時代、文学は必要であるはずだと思いたい。2013/02/05
aoneko
3
1993年から2011年までの日本の文学作品に対する時評集。著者の考える「世界文学」の定義、そもそも本書自体度々世界各地を移動するなかで書かれていることも興味深いし、共感に安住することへ恐れを感じ、「何だこりゃ」と世界が謎に満ちていると示すことの可能性についての話なんてとくに印象的だった。遡って読んでみたくなる本も増えます。 2013/05/06
askmt
1
世界文学の中の日本文学という視線の中に、日本固有の問題系から世界に接続する線もあるんじゃないかな、とちょっと思った。2016/09/14
金糸雀
0
やっと読み終わった。図書館本だったけれど、購入したくなった。色んな本が印象に残る。解くには、「若冲の目」と日本語で小説を書くイラン人女性🎵2019/04/06