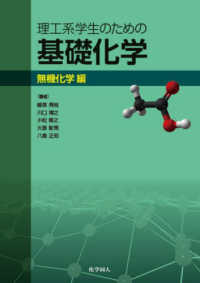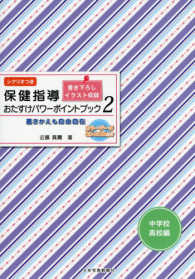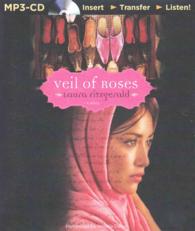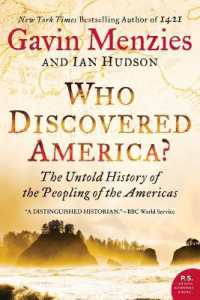内容説明
ハイデガー、フランクフルト学派からポストモダン以降まで。資本主義を根底から批判し、近代の本質を暴露した、思考の最前線を“危機の時代”のなかで再び召還する。
目次
第1回 ハイデガーからフランクフルト学派まで
第2回 実際に『啓蒙の弁証法』を読んでみる。1
第3回 実際に『啓蒙の弁証法』を読んでみる。2
第4回 実際に『啓蒙の弁証法』を読んでみる。3
第5回 フランクフルト第二世代―公共性をめぐる思想
第6回 ポストモダン以降
後書きに代えて―現代ドイツ思想史の“魅力”
著者等紹介
仲正昌樹[ナカマサマサキ]
1963年広島生まれ。東京大学総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程修了(学術博士)。現在、金沢大学法学類教授。「ポストモダン」が流行の80年代に学生時代をすごす。西洋古典、現代ドイツ思想、社会哲学、基礎法学などの“マトモ”な学問から、テレビ、映画、アニメ、はたまた松本清張などの“俗っポイもの”まで幅広くかつ真剣に議論を展開し、また医療問題にも取り組む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
退屈しのぎ本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たばかるB
15
ずっしりとした仲正講義。いや分かりやすかった。全体の流れをつかむため、啓蒙の弁証法の部分は流し読みでハーバーマス以降の思想の流れを追う。フランス現代思想が日本と同時期にドイツに入り、理性を重視するフランクフルト学派は退潮。政治学の議論へと接近したのがホネット、「教科書的に」アドルノ~ハーバーマスをまとめた。戦後ドイツ思想はナチの影響で、ドイツロマン主義的な理性の外の議論に接近できなかった、と言われている。2022/06/21
白義
8
フランクフルト学派、特にアドルノたちの「啓蒙の弁証法」を重点的に解きほぐしながら、ハイデガーからスローターダイクまでのドイツ現代思想を講義した好著。単純に一言で語るのを拒むアドルノたちの批判理論の核心の、重要な部分を冷静に時に俗なたとえも交えながら扱えていて仲正さんらしい一冊に仕上がっている。アドルノ=エリート主義の大衆文化批判、現代思想っぽい合理性批判だけの学者だと侮ると痛い目を見ること間違いなし。仲正氏らしくアドルノのヘルダーリン論なんかも紹介している2013/01/12
ぷるぷる
6
「啓蒙の弁証法」を解説を中心としたタイトル通りにドイツの現代思想の講義の本。歴史的背景を体系的に説明してくれるのでユーロコミュニズムからフランクフルト学派が自分の中で整理することができました。「啓蒙の弁証法」の中で取り上げられている神話の説明もそうだったのかと勉強させられましたし、文化産業についての捉え方も大衆娯楽に行き着くまでの根底にある西欧思想を少なくとも分かった気にはさせてくれます。所々にアニメの話なんかが散りばめられているのもお茶目です。分量もあり難しくもありますが割とスラスラ読めて有り難いです。2021/01/25
NагΑ Насy
5
アドルノを中心に読みながら、ハイデガーからベンヤミン、ハバマス、フランス構造主義経由のドイツのポストモダン、ベルリンの壁崩壊後のあたりまでの20世紀のドイツ思想を概観できた。しろうとには哲学タームの解説が便利。ただニーチェとかロマン主義に繋がると即ナチ圏=危険て書くのは短絡しすぎでないか? 敗戦後で人材は散りじりとなり左にいけばソ連共産主義が右にいけばナチの亡霊がというなかで思想はハーバマス以外まったく行き詰まりの様相。2013/10/06
esehara shigeo
4
やっぱ中心になっているアドルノが面白くて、まさに「今起きていること」というのは、殆ど『啓蒙の弁証法』で斬れることであるという実感が持てる一方、本書で指摘されている通り、アドルノは何でも批判してしまうので、とにかく出口が無い。それは「否定神学的」な身振りではあるし、のちにハーバーマスに批判されるのだが、とはいえ使える部分を分解して使えばいいのではないかという気がするし、そういう本になっている。一方で、やはりハーバーマスは「常識的」というか、確かに社会学的には正当だが退屈なんだよな、というのは否めない。2019/08/02