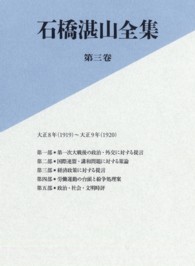内容説明
それは果たして、どのような「勝利」だったのか?六〇年安保以後、あるいは現在においてもなお、日本の「知識人」の代表的存在と見なされ「戦後最大の思想家」とさえ評される吉本隆明は、どのようにそのヘゲモニーを確立していったのか。批評家としてデビューした1950年代から60年代にかけて彼が行なった論争と時代背景の精緻な分析をとおして解明する。「知の巨人」の実像に迫る、入魂の書き下ろし長篇評論。
目次
序章 「普遍的」知識人の誕生―ジッドからサルトルへ/小林秀雄から吉本隆明へ
第1章 一九五〇年代のヘゲモニー闘争―「文学者の戦争責任」と花田清輝
第2章 ドレフュス事件としての六〇年安保―共産主義者同盟と武井昭夫
第3章 六〇年安保後の知識人界―黒田寛一と「真の」前衛党
第4章 市民社会と大学の解体―丸山真男と六〇年代
終章 「六八年」へ―サルトル来日、そして岩田弘/廣松渉/津村喬
著者等紹介
〓秀実[スガヒデミ]
文芸評論家・近畿大学国際人文科学研究所教授。1949年新潟県生まれ。学習院大学中退。「日本読書新聞」編集長、日本ジャーナリスト専門学校専任講師などを経て、2002年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mstr_kk
4
すがさんと吉本ということで、『革命的な、あまりに革命的な』と『1968年』の後に読みました。 いちばん分からなかった本です。 それぞれの段落で言われていることは分かるし、すらすら読めるのに、全体が像を結ばない……。 要再読です。2015/04/09
肉欲棒太郎
3
「戦後最大の思想家」吉本がいかにして思想界のヘゲモニーを確立していったのかを解明する評論であることを想定して読み始めたが、読後感としてはむしろ、吉本は登場人物の一人に過ぎないと言っても過言でないほど吉本以外の思想家たちについての考察が充実しており、その意味で本書は吉本論というよりは、トータルな戦後の日本思想史論と言える。吉本の知識人としての影響力はあくまで60年安保のものであり、「68年」とは本質的に無縁であるという著者の指摘は興味深い。2016/06/05
ミスター
2
武井が大東亜戦争から自由浮動型の知識人を読み取ったという理解は全くその通りで、敗戦からインターナショナルに開かれた点こそ武井のもっとも評価されるべき点の一つだろう。吉本以外の花田や武井、谷川雁の解説書としてとても有益。2019/02/08
2
再読。スガちんの中では一番読みにくい笑 だけど物凄く勉強になるし、実はスガちんの中でも一番好きな本だったりする。歴史=文脈というのが如何に大切なものかを教えてくれる。読んで驚くのだが、この本の中で吉本の思想はほとんど言及されていない。当時の吉本の位置を「呪われた知識人」というタームで分析しながら、1960年における日本の「ドレフュス事件」=「安保闘争」をメルクマールに如何にヘゲモニーを握るのか、ある種の「吉本神話」の解体が目論まれている。情報量や自分の知識が圧倒的に不足していることを痛感するのもまたよし。2017/05/11
受動的革命
1
60年安保=ドレフュス事件と「自由浮動型知識人」の誕生という図式を梃子に、吉本の知的ヘゲモニーの条件と成立過程が精緻に検証されている。無垢であるがゆえに疎外された存在というあらかじめのプログラムによって普遍的知識人たりえた吉本に対して、そもそも疎外とはまったく異なる地平に立った花田・武井に評価が与えられている。 後書きによれば、吉本というオイディプスに対する「アンチ・オイディプス」の企図があるらしい。著者が叛旗派総括の小冊子に本名名義で論考載せていることもあり、元叛旗の人たちのためにも書かれているのでは。2025/03/24